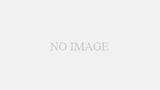石碑には経典や祈祷書からの引用文が刻まれていることがしばしばあります。その中には現在もよく知られていて実際に唱えられるものもありますが、今ではほとんど忘れられているものもあります。その出典が(私には)わからないものも少なくありません。ここでは藤沢市の石碑に刻まれた経文のいくつかを、見かけることが多い順番にその出典とともに紹介したいと思います。経文の記述は特に記載がなければSAT大正新脩大藏經テキストデータベースを引用しています。したがって実際の石碑に刻まれている文字とは若干異なる場合があります。
1 妙法蓮華経 化城喩品第七
願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道
これは現在も回向文としてよく知られている偈文で、藤沢市の石碑に刻まれた経文としては最も多く十数基に見られます。そのうち一番古いものは用田の寿昌寺にある読誦塔で、この塔には年号が書かれていないものの寿昌寺八世の銘があることから十八世紀前半のものであることがわかります。これ以外は現代のものを除けばすべて十八世紀後半に造られたものです。地蔵菩薩塔、三界万霊塔、読誦塔に刻まれていることが多いようです。
2 仏説延命地蔵菩薩経
一者女人泰産 二者身根具足 三者衆病悉除 四者壽命長遠 五者聰明智慧 六者財宝盈溢 七者衆人愛敬 八者穀米成熟 九者神明加護 十者證大菩提
毎日晨朝入諸定 入諸地獄令離苦 無佛世界度衆生 今世後世能引導
我從過去 無量劫來 見諸六道 一切衆生 法性同體 無始無終 無異無別 無明異相 生住異滅 是得是失 起不善念 造諸悪業 輪廻六趣 生生父母 世世兄弟 悉成佛道 後我成佛 若殘一人 我不成佛 若知此願 二世所求 悉不成者 不取正覺
仏説延命地蔵菩薩経はその最初に不空訳と書かれていますが、実際には日本で作られた経典です。偽経ながらよくできていて広く読まれたようです。最初の引用は釈迦の言葉で地蔵菩薩の功徳を説いたもので、西富の清浄光寺の地蔵菩薩道標(1856)に見られます。次は打戻の盛岩寺の地蔵菩薩塔(1770)、下土棚の善然寺の地蔵菩薩念仏塔(1754)、大庭の宗賢院の地蔵菩薩塔(1793)、最後の引用は渡内の天嶽院の地蔵菩薩塔(1764)にそれぞれ見られ、これらは地蔵菩薩自身の言葉で衆生の救済を語るものです。この経典の全文は例えばこちらで見ることができます。
3 一切如来心秘密全身舎利宝篋印陀羅尼経
若有有情能於此塔 一香一華禮拜供養 八十億劫生死重罪一時消滅 生免災殃死生佛家 若有應墮阿鼻地獄 若於此塔 或一禮拜 或一右遶 塞地獄門開菩提路
若有有情能於此塔 種植善根 必定於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
密教系のこの経典は、写経して宝篋印塔に収めると現世利益があるとされ宝篋印塔に刻まれます。この経典にはいくつかの異本があり、ここにあげた二文は異なる祖本によるものです。最初の引用は用田の寿昌寺(1771, 1938再建)、菖蒲沢の個人墓地(年代不明)、本町の荘厳寺(1793, 1883再建)、鵠沼神明の鵠沼墓地(1764)にそれぞれある宝篋印塔に刻まれています。このうち鵠沼墓地の旧家高松家の宝篋印塔の引用は上記よりかなり長いものです。二番目の引用は大鋸の感応寺墓地(1801)に見ることができます。これらの宝篋印塔はいずれも装飾性が強いもので、多宝塔に近い構造をもっています。
4 妙法蓮華経 観世音菩薩普門品第二十五
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能爲作依怙 具一切功徳 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮
これは観音経とも呼ばれる、観世音菩薩の功徳を説く妙法蓮華経の一章の偈文の最後にあるものです。禅語の福寿海無量はこの福聚海無量の「聚」を「寿」に変えたものとされています。高倉の路傍にある庚申塔(1675)、渡内の慈眼寺の百番巡礼塔(1857)、本鵠沼の原の辻の西国巡礼塔(1795)に見られます。また打戻の盛岩寺にはこの訓読文が刻まれている現代の塔もあります。なお慈眼寺の百番巡礼塔以外はすべで具一切功徳以下の句が引用されています。
5 妙法蓮華経 薬草喩品第五
汝等所行 是菩薩道 漸漸修學 悉當成佛
薬草喩品は草木の茂る姿をたとえとして仏の教えを説いたもので、この引用はその偈の最後にみられるものです。辻堂元町の宝珠寺の庚申塔(1683)に見ることができます。なおこの塔では汝等とあるべきところ如等と刻まれていますが、汝を如と記す例はしばしばあります。
6 妙法蓮華経 方便品第二
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
この引用は仏の教えの本質を語る方便品の最後の長い偈の中にあるものです。5とおなじく辻堂元町の宝珠寺の庚申塔(1683)に刻まれています。
7 妙法蓮華経 陀羅尼品第二十六
爾時藥王菩薩即從座起 偏袒右肩合掌向佛 而白佛言 世尊 若善男子善女人 有能受持法華經者 若讀誦通利 若書寫經卷 得幾所福 佛告藥王 若有善男子善女人 供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛 於汝意云何 其所得福寧爲多不 甚多世尊 佛言 若善男子善女人 能於是經 乃至受持一四句偈 讀誦解義如説修行 功徳甚多 爾時藥王菩薩白佛言 世尊 我今當與説法者 陀羅尼呪以守護之 即説呪曰 (以下陀羅尼呪の音訳)
これは陀羅尼品の最初の部分で、薬王菩薩が仏との対話の中で信者を守護するとの宣言とともにその呪を述べています。大庭の宗賢院の宝塔(1796, 1931再建)に陀羅尼呪も含めて長文が刻まれています。この塔は大乗妙典すなわち妙法蓮華経の読誦塔でありまた西国坂東秩父百番の観音供養塔でもあり、さらに領主の武運長久を祈念するとともに施主自身の一族の菩提供養と繁栄を願うというかなり欲張った多目的の塔です。
8 不空羂索毘盧遮那佛大潅頂光真言
唵 阿謨伽 尾嚧左曩 摩賀母捺囉 麼抳 鉢納麼 入嚩攞 鉢囉韈哆野 吽
この引用はいわゆる光明真言で、この経典では光明真言の功徳として一切の罪と業を滅ぼし極楽に往かせると説きます。藤沢市には梵字で光明真言が刻まれた塔が8基ありますが、高倉の東勝寺の地蔵菩薩塔(1673)には漢字で光明真言が書かれています。地蔵菩薩塔に光明真言が見られるのも市内ではこれが唯一です。これは呪文として音訳されたものですから、意図的に平易ではない漢字を用いて呪文らしくしています。
9 法句経
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
これは最古の経典のひとつとされている法句経の偈にあるもので、七仏通誡偈とも呼ばれ現在も禅宗で唱えられるほか掛け軸でもよく見かけます。本町の六本松古戦場と呼ばれる一角にある庚申塔(1845)に最初の二句が刻まれています。
10 薬師琉璃光如来本願功徳経
我之名號一經其耳 衆病悉除身心安樂
この経典は薬師如来の功徳を説くもので薬師経として知られているます。この一節は、薬師がまだ菩薩であったときに発した十二の大願のうち第七番目の記述からの引用です。西俣野の花応院にある写経塔(1773)に刻まれています。
11 仏説無量寿経
天下和順 日月清明 風雨以時 災厲不起 國豐民安 兵戈無用 崇徳興仁 務修禮讓
仏説無量寿経は無量寿経の漢訳本の一つで、浄土宗や浄土真宗の根本経典の一つです。この一節は祝聖文と呼ばれるもので、今でも正月の法要などで唱えられます。10と同じ西俣野の花応院にある写経塔(1773)に天下和順から兵戈無用までが刻まれています。なお花応院は禅寺ですが、この写経塔の銘にはかつて花応院の近くにあり天保年間に焼失した浄土宗法王院十王堂の僧名が刻まれており、この塔は十王堂にあったと考えられます。
12 十二礼
稽首天人所恭敬 阿彌陀仙兩足尊 在彼微妙安樂國 無量佛子衆圍繞
阿弥陀仏の功徳を称賛する偈である十二礼の最初の句です。現在でも十二礼は浄土真宗で唱えられるものです。遠藤の寶泉寺の徳本上人名号塔(1818)に刻まれています。この塔は以前こちらで紹介しました。なお十二礼は原典が知られておらず、単独で成立したものなのかどうかもわかっていません。
13 観無量寿経疏 玄義分巻第一
願以此功徳 平等施一切 同發菩提心 往生安樂國
仏説観無量寿経の注釈書である観経疏玄義分の巻頭の偈の最後の一節です。浄土宗や浄土真宗では回向偈として知られるものです。鵠沼海岸の本真寺の三重塔(1917)にみることができます。この塔は、滋賀県東近江市の石塔寺にある阿育王塔と呼ばれる日本最古の石造三重塔(奈良時代前期 重要文化財)を写したものです。
14 諸回向清規式 巻第二 地蔵菩薩諷経
菩薩大悲體遍滿六道中 滅除重業障如影不暫難
諸回向清規式は臨済宗で用いる回向文や儀式作法を集成したもので、天倫楓隠によって永禄九年(1566)に編纂され明暦三年(1657)に刊行されました。この一節は地蔵菩薩に対する回向文からの引用です。獺郷の東陽院入口前の辻にある地蔵菩薩像の台石(1742)に刻まれています。
15 浅学教導集 巻第十一 八 念仏講塔婆
諸教所讃多在彌陀 故以西方而爲一准矣 蓋以 称名念佛者 現受無比樂之善因 後生清淨土之津梁 越 村落老壮 尊重粛々 頼無量光本願 勤厚綿々 結念佛講良縁 拜瞻三諦聖容 送於多念 口誦六字名号 滿於數返 茲㠯 築毗盧遊戯黄壚 致功德樹木供養 若爾 同志檀主 今世之間 蒙安富安榮祥瑞 異滅後昇 上品上生廣閣 乃至 三界衆類 共詣唯心淨刹 六道群機 同謁已心彌陀
浅学教導集は万治三年(1660)に天台僧光憲によって書かれた回向文集で、ここにあげたものは念仏講による造塔供養のための二つある経文のうちの一つの全文です。12と同じく遠藤の寶泉寺の徳本上人名号塔(1818)に刻まれています。浅学教導集は大蔵経には含まれていませんが、国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができます。
16 修験道無常用集 巻上 通用塔婆之部
地藏菩薩 以大慈悲 若聞名号 不堕黒闇
修験道無常用集は修験道における葬儀の次第を記載したもので、延享二年(1745)に修験者鑁清により編纂されました。この引用は五七日法要をつかさどる地蔵菩薩の句です。あるいはこの句自身別の経典からの引用のように思われますが出典はわかりません。大庭の北ノ谷共同墓地の六地蔵(1792)のひとつにこの句が刻まれています。修験道無常用集は日本大蔵経第37巻に含まれており、国立国会図書館デジタルコレクションで本文を見ることができます。
17 出典不明
法性真如放猛火 輪廻生死焼罪苦 法尒无作遊■土 實相成就風颯々
(■は梵字のア)
漢字で書かれた句に梵字が一つだけ含まれるという異例なこの一文は、16と同じ大庭の北ノ谷共同墓地の六地蔵(1792)に刻まれています。この文と異体字や梵字も含め完全に同一のものが昭和初期に出版された悉曇種子類聚という書籍にあり、国立国会図書館デジタルコレクションで全文を見ることができます。この書籍の原本は沙門澄禅が寛永七年(1630)に書いたもののようですが、昭和初期版には明らかに新しい記述があり原本とはかなり差があるはずで、原本にこの句があったかどうか未確認です。
18 出典不明
六道能化 放光十万 大悲本願 願海無量
遠藤の寶泉寺の地蔵塔の台石(1830)に見えるものです。この塔は台石だけが残っており地蔵菩薩像はありません。台石にはこの塔の造立の経緯も書かれており、それによると壊れてしまった地蔵塔の再建塔のようです。地蔵菩薩を賛美する偈にありそうな句ですが出典はわかりません。あるいはこの塔の造立者が作ったものなのかもしれません。
19 出典不明
□大慈悲力 速覚長夜眠 永破生死夢 出三界火宅 望九品蓮臺
葛原の乗福寺の地蔵菩薩塔(1763)の台石に刻まれています。他の面の記述からこの塔は十四才で亡くなった童子の供養のために建てられたものであることがわかります。ここにあげた詩的な句は引用かあるいは造立者の創作によるものなのか不明です。
この他にも経典に起源を持つ短い単語やその組み合わせが刻まれているものはたくさんあります。また塔の目的に応じて文に手を加えられているものもあります。これらは経典が生きた言葉であったことを示しています。以下に、経典からの引用と生きた言葉の両方がよく書かれている大庭の北ノ谷共同墓地にある六地蔵の銘文全体を紹介します。この共同墓地の歴史については墓地内にある記念碑に次のように書かれています。
昔の農村では自分の畑や山の片隅に個人墓地をつくっておりました 私たちの賢明な先祖は江戸の中ごろそれら個人墓地をこの地に集約し他村に先がけて共同墓地をつくったのです それからほぼ二世紀静かな村にも都市化の波が押し寄せこの共同墓地も藤沢市西部土地区画整理事業によって移築されることになりました 私たちは寺の跡地の払い下げを受けたのを機会にさらにそれぞれ土地を出し合って形も規模も一新する秩序ある墓地に改装致しました
昭和五十三年春 工事は円滑に終了し祖先を敬いここに記念碑を建立する次第です
昭和五十三年四月吉日建之
ここにあった寺とは新編相模国風土記稿(1841)の大庭村の項に「彌陀堂 石川村自性院持 發願山千手院の號あり」と書かれている浄土宗寺院です。明治初年に廃寺となりましたが、歴代墓碑とされる無縫塔群や千手院と刻まれた寛文十二年(1672)の庚申塔が残っています。明治十二年(1879)の皇国地誌村誌稿によればこの堂は東西六間五分南北十壱間面積七十三坪とあり、これは今の墓域の縦横半分で面積にして四分の一程度の小堂であったことがわかります。現在六地蔵は歴代墓碑や弘法大師塔などとともに整然と並べられています。


地蔵菩薩塔(六地蔵) 寛政四(1792)
一 伏息地蔵(天)〔錫杖・宝珠?〕
[基礎正面]〔梵字カ〕休息地藏大菩薩 爲利六道持六輪錫 願以之功德普及於一切 我等與衆生皆供成佛道
[基礎左面]法性真如放猛火 輪廻生死焼罪苦 法尒无作遊〔梵字ア〕土 實相成就風颯々
《原文》休息(ママ)逰(遊)
二 伏勝地蔵(人間)〔天蓋〕
[基礎正面]〔梵字イー〕伏勝地藏大菩薩 爲飢走者作諸井草 三界萬霊一切含識 出離生死徃生淨土
《原文》𭇥(含)
三 禅林地蔵(地獄)〔錫杖・宝珠?〕
[基礎正面]〔梵字イ〕禅林地藏大菩薩 爲熱惱者作清凉水 地蔵菩薩以大慈悲 若聞名号不隨黒闇
[基礎右面]于時寛政四壬子稔中秋 奉造立六地藏尊 大庭村 北之谷|表郷 講中
《原文》𱫚(熱)
四 無二地藏(餓鬼)〔合掌〕
[基礎正面]〔梵字カー〕無二地藏大菩薩 爲貧窮者作如意宝 施入面々先祖代々 一切聖霊成等正覚
五 諸龍地蔵(修羅)〔数珠〕
[基礎正面]〔梵字イ〕諸龍地藏大菩薩 爲露形者作諸衣服 寛政三亥年 〔梵字ア〕體性智等信女霊位 霜月初九日 施主北ノ谷小左衛門
六 護讃地蔵(畜生)〔幢幡〕
[基礎正面]〔梵字コ〕護讃地藏大菩薩 爲病疾者作妙良藥 願主講中二世安樂 家内安全子孫繁栄
《原文》𭼋(疾)
この表では六体の地蔵菩薩塔の銘を右から順に記載していますが、おそらくこれは元の並びではなく、本来は右から地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天となるよう三、四、六、五、二、一の順番で並んでいたと考えられます。実際三だけに右面の銘があり、また一だけに左面の銘があることもそれを裏付けています。基礎石の文字は楷書でしっかりと彫られており読みやすく、風化も進んでいないため今もはっきりと読み取ることができます。
施主の小左衛門は大庭の旧家金子家の人物で、金子家当主は明治まで代々小左衛門を名乗っていました。『寒川町史研究第4号』(1991)によれば、高野山高室院文書の寛政八年の記録に大庭谷戸分の名主小左衛門の名が見えます。この六地蔵の施主その人でしょう。最後の金子小左衛門氏は大庭入村の名主で明治末に亡くなりました。戦前と戦後の長きにわたって藤沢市長をつとめられた金子小一郎氏の祖父にあたる方です。金子家の立派な墓碑群をこの北の谷共同墓地に見ることができます。