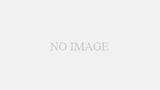藤沢市内でもっとも数の多い石仏像といえば地蔵菩薩でしょう。剃髪した僧侶の姿で二世安楽をもたらしてくれる地蔵菩薩は時代を超えて人気です。地蔵菩薩ではない仏像に赤い前掛けがされていることもしばしばですから、石仏像といえばお地蔵さん思う人も少なくないようです。これまで紹介した中でも、亀井野の亀井神社では不動明王とその脇侍たちに赤い前掛けがされていました(こちら)。また羽鳥には「おしゃれ地蔵」と地元で呼ばれている双体道祖神があります。天明八年(1788)の年号が刻まれていたとされるこの道祖神がいつからそのように呼ばれるようになったかは不明ですが、今も願をかける人々によって像の顔にお化粧がされています。
次に多い石仏像は観音菩薩です。墓碑に彫られているものも含めると地蔵菩薩に匹敵するくらいの数になるかもしれません。観音菩薩には像容の異なる別身がいろいろありますが、大半は聖観音と如意輪観音です。ただし如意輪観音は女性の墓碑に彫られることが圧倒的に多く、それ以外のものは十数基にとどまります。これら以外の観音の石仏像は少なく、市内では馬頭観音が二十基程度で十一面観音や千手観音はそれぞれ十基もありません。これら五身の観音(聖観音、如意輪観音、馬頭観音、十一面観音、千手観音)に准胝観音あるいは不空羂索観音またはその両方を加えたものは六観音あるいは七観音と呼ばれていますが、ここではこれらをとりあげます。
市内で六観音あるいは七観音の石像がそれとわかる形で並べられているのは江の島の延命寺一か所しかありません。延命寺は『新編相模国風土記稿』(1841)の江島上の坊の項に「念仏堂 延命寺の号あり、墓守の僧住す」とのみ記されてあり、その後おそらく明治の神仏分離の時に廃寺となりました。現在は昭和38年に作られた納骨堂と古い石碑を残すのみで、観光客が訪れるところではなくいつもひっそりしています。ここに大型の観音菩薩像六体が並べられています。年号が刻まれていないので造立年はわかりませんが、隣に並んでいる同じくらいの大きさの六地蔵像には宝永三年(1706)の銘があり、顔の彫りが似ているのでこの六観音も同じころに造られたものなのかもしれません。

1 如意輪観音菩薩
[正面]〔六臂如意輪観音菩薩半跏像〕
[正面下部]妙栄 貞春 叶折言 貞照 鏡栄 妙□ 栄□
2 千手観音菩薩(?)
[正面]〔八臂千手観音菩薩立像〕
[正面下部]一宗圓 妙壽 貞心
[右面]材木座村 ……
3 聖観音菩薩
[正面]〔聖観音菩薩立像〕
[正面下部]全如 清■ 道壽 誓円
[右面]爲法界 ……(爲法界万霊とあったか)
《原文》𭐖(壽)慧あるいは㥯の異体字か(■)
4 准胝観音菩薩(?)
[正面]〔准胝観音菩薩立像〕
[正面下部](銘なしあるいは風化摩滅)
5 十一面観音菩薩
[正面]〔十一面観音菩薩立像〕
[正面下部]英樹清□ 道蓮秋□
6 馬頭観音菩薩
[正面]〔六臂馬頭観音菩薩立像〕
[正面下部]十郎兵衛 道□ 教清妙吟 淨入智春 …… ……
『藤沢市の石仏』(2003 藤沢市教育委員会)では右から、如意輪観音・千手観音・聖観音・准胝観音・十一面観音・馬頭観音としています。しかし千手観音は八臂しかありませんし、准胝観音も二臂で合掌する姿は聖観音と変わりません。全体的に彫りは素朴で像容も簡素化されている感じがします。これらの像には正面下部に合計二十名ほどの法名と思われる名が記されているほか、一部右面にも銘があるのですが、隣接する像との間隔が狭く、また文字も不明瞭なので判読が困難です。かろうじて読み取れた文字によれば、材木座村(現鎌倉市材木座)から三界万霊の供養塔として奉納されたもののようです。
ところでこの六観音の左側には六地蔵、右側には別の如意輪観音が並べられていますが、どれも保存状態が良く、海の近くに何百年もあった石像とは思えません。きっと雨風から守られたところに置かれていたのでしょう。しかも江の島では明治初年の神仏分離の時に仏教にかかわるものはかなり徹底的に破棄されていますので、これらの像がよく無事に残っていたものです。
江の島にはもう一か所六観音と思われる石仏像が残っている場所があります。それは現在第一岩屋と呼ばれているところで、ここにはまざまな種類の石塔が並べられており、それらの位置と名称を示す看板も掲げられています。その中に六つの観音像(如意輪観音・不空羂索観音・十一面観音・千手観音・聖観音・馬頭観音)を見ることができます。看板では仏像坐像、観音立像と書かれているところがそれぞれ不空羂索観音、聖観音にあたります。これらの観音像は今はばらばらに置かれていますが元は六観音として奉納さられたと考えられます。







7 如意輪観音菩薩
[正面]〔四臂如意輪観音菩薩半跏像〕
8 不空羂索観音菩薩
[正面]〔三面六臂不空羂索観音菩薩座像〕
9 十一面観音菩薩
[正面]武州豊嶋郡江戸浅草奥田九兵衛 〔十一面観音菩薩立像〕 寛文四年甲辰三月吉祥日 祇言
10 千手観音菩薩
[正面]六観音□□ 〔千手観音菩薩立像〕 ……
11 聖観音菩薩
[正面]〔聖観音菩薩立像〕
12 馬頭観音菩薩
[正面]〔三面八臂馬頭観音座像〕
岩屋内は暗いので像をよく見るためには懐中電灯が必要です。どれも小さいながら状態はよく、像容にまぎれはありません。このうち十一面観音像には銘がきれいに残っており、寛文四年(1664)に浅草の奥田九兵衛が奉納したものであることがわかります。かなり古いものです。なお『近世初期遊女評判記集 研究篇 』(1965 古典文庫)によれば、このころ浅草新吉原の新町に亀甲屋奥田九兵衛という人物がいたようですが、あるいはこの六観音奉納者と同一人物なのかもしれません。また千手観音像の正面右下には風化で読みづらいですが六観音と刻まれているように見えます。正面左下にも文字がありますが読み取れません。
第一岩屋に残る石塔には銘がないか、あっても風化で読み取れなくなっているものが多く、その由来を知ることは困難です。唯一それがはっきりしているのが弘法大師像で、岩屋内に二基ある弘法大師座像のうち大きい方は鎌倉市手広の宝積院にあったものだとされています。これは文政三年(1820)から四年にかけて造られた相模国準四国八十八箇所の大師像の一つで、宝積院が廃寺になったのち江の島に移されました。相模国準四国八十八箇所の歴史と各札所に置かれていた弘法大師像の現況については、「鵠沼を語る会」が調査作成した文書に詳細に書かれており大変参考になります(こちら)。参考までに岩屋に残る2つの弘法大師像とその銘を紹介します。なお風化のため銘は読みづらく、誤っているところがあるかもしれません。


13 弘法大師
[正面]〔弘法大師座像〕
[基礎右面]爲 後生 菩提
[基礎左面]二世 安楽
14 弘法大師
[正面]〔弘法大師座像〕
[基礎右面]文政三辰年 十一月吉日 石工 江戸深川 いしや源八
さて市内にはもう一か所、七観音の一部と思われる石仏像が残されているところがあります。それは大庭にある真言宗寺院の成就院です。ここには七観音以外にも興味深い石仏像が残されているので、次項でまとめてとりあげたいと思います。