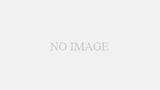藤沢市の西北部、御所見地区の南に位置する遠藤はかつては自足自給の純農村地帯でした。そのころの遠藤の様子は、『遠藤の昔の生活』(1980年 藤沢市教育文化研究所)にくわしく描かれています。その後昭和三十年代にはじまった開発により、遠藤はその東部に工場地帯、南部に湘南ライフタウン、西部に慶応義塾大学湘南キャンパスが作られ近代都市へと大きな変貌をとげていますが、一方で中央部や北部は昔ながらの農村地帯の姿を色濃く残しています。
遠藤の中心は、現在遠藤市民の家がある遠藤一番地であり、この東側に隣接するのが旧遠藤村の鎮守であった御嶽神社です。御嶽神社がいつ創建されたかは不明ですが、『新編相模国風土記稿』(1841)に御嶽神社に関する慶長五年(1600)の記事があるので、少なくとも16世紀に遡る歴史をもつと考えられています。山岳信仰の神社らしく本殿は富士山に向かって建てられており、天気が良ければ境内から富士山を見ることができます。
御嶽神社は明治になるまで大験寺と呼ばれる別当寺の管理下にありました。大験寺は当山派相模本山の修験道寺院で、高座郡内に6つの末寺を持つ触頭寺でした。以前紹介した西俣野の御嶽神社の別当寺であった神礼寺(こちら)も大験寺の末寺でした。大験寺はこのような有力寺でしたが、明治初年の修験道廃止令により他の多くの修験道寺院とともに廃寺となりました。寺があったとされる御嶽神社階段下の一角は今は竹林となっており、往時をしのばせるものは何も残っていません。

大験寺の歴史について知られていることはほとんどなく、新編相模国風土記稿にも「遠藤山と号す当山修験醍醐三宝院末 秋葉社、稲荷社、白山社、富士浅間社、已上大験寺持」とあるだけでその創建や事蹟に関する記述はありません。現在唯一残っているものは、御嶽神社の西に位置する曹洞宗寺院である宝泉寺境内にある文政元年(1818)の巨大な徳本名号塔です。これは大験寺から移設されたものと言われており、「大験寺住英須法印謹誌」との銘がある経文が基礎石に刻まれています。
大験寺は廃寺となりましたが、大験寺歴代の墓地は御嶽神社から400mほど南東にある遠藤中原の一角に今もひっそりと残っています。畑の奥の草むらの中にあり見つけにくいところです。墓碑は草に深く埋もれているものや風化倒壊しているものもあるので正確な数はわかりませんが、江戸時代のものは30基ほど見られます。ここは藤沢市の文化財総合調査報告書では取り上げられておらず、『藤沢市の石仏』(2003 藤沢市教育委員会)に江戸初期の一基と明治時代の一基だけが掲載されています。

先日久しぶりにここを見に行ったら、部分的に草が刈られ地面がシートで覆われており、多くの墓碑の銘文が見やすい状態になっていたので読んでみると、大験寺歴代が開山から十代以上たどれることに気づきました。草中に埋もれている数基は調べきれていませんが、ここに墓碑のある男性はすべて僧籍者のようです。下記にこれらの銘文を示します。1番から7番までは何世かが銘文からわかるのでその順に、8番以降は銘の年号順に並べています。
1 角柱尖頭(開山、二世、三世)弘治元(1555)慶長四(1599)
[正面]〔梵字ア〕開山泉藏大僧都不生位
[右面]弘治元卯天 二世永昌大僧都 七月十三日
[左面]慶長四亥年 三世昌全大僧都 四月二十二日
2 角柱重頭(四世)寛永五(1628)寛永十八(1641)
[正面]四世 寛永五戊辰天 〔梵字ア〕権大僧都春林善秋上𫝶 正月廿三日
[右面]寛永十八辛巳天 月霜貞心禅定尼㚑位 十月七日
[左面]鏡法院父母
《原文》𫞐(權)
3 角柱重頭(五世、六世)万治二(1659)寛文十三(1673)元禄十一(1698)
[正面]五世 万治二癸亥三月十三日 〔梵字ア〕権大僧都法印□光秋本上𫝶 乘宝院父
[右面]寛文十三丑八月七日 光安秋月禅定尼㚑位 乘法印息娘
[左面]六世 元禄十一戊刁十月廿三日 〔梵字ア〕権大僧都法印□岳性旲大德 大教院父
《原文》𫞐(權)乘法印(ママ)
4 角柱重頭(七世)享保三(1718)宝永三(1706)正徳五(1715)貞享三(1686)
[正面]七世 享保三戊戌二月廿二日 〔梵字ア〕 権大僧都大越家大教院玄秀法印 覚位← 大乘院父
[右面]〔梵字カ(地蔵菩薩)〕暁露童子 宝永三戌二月三日 観央童子 同年同月廿四日 一漚童子 正德五乙未六月十日
[左面]貞享三刁年 正善院了因德祐 九月廿日
《原文》𫞐(權)⿱一央(央)
5 角柱弧頭(八世)安永九(1780)
[正面] (上部剥離欠落) 〔梵字ア〕大越家阿闍梨秀全法印 (下部)本不 生位
[右面]大乗院生年九十二歳
[左面]安永九子天 四月六日
6 角柱弧頭(九世)宝暦四(1754)
[正面]九世 〔梵字ア〕普門院大越家教順大僧都 覚位←
[右面]宝暦四戌天
[左面]十月十九日
7 角柱弧頭(十世)寛政九(1797)
[正面]十世 〔梵字ア〕大教院□要阿舎梨位
[右面]寛政九巳天
[左面]十二月廿二日
《原文》□は臨あるいは儉の異体字か
8 角柱弧頭 享和二(1802)
[正面](上部剥離欠落)法師不生位
[右面]享和二□年
[左面]十一月丗日
9 角柱尖頭 文政十(1827)
[正面]〔梵字ア〕法印大先達英須大法師位
[右面]文政十亥年十二月十一日
《原文》⿰亻師(師)
10 角柱弧頭 文政十二(1829)
[正面]文政十二丑年 〔梵字ア〕権律師惠雲法師位 六月三日
《原文》⿰亻師(師)
11 自然 明治十八(1885)明治三(1870)明治二十二(1889)
[正面]明治十八年八月五日 遠藤知英祀念碑
[背面]明治三年六月十八日 多婦止美大姉 廣道院浄照永久清大姉 明治廿ニ年六月九日
[背面下部]小出村遠藤 周施方← 記名イロハ順 〔二十四名氏名列記〕
《原文》祀念碑(ママ)𭴫(照)岀 (出)
12 自然 明治二十四(1891)大正二(1912)
[正面]明治二十四年九月六日死ス 遠藤忠造之墓 行年五十二歳
[背面]大正二年九月六日 遠藤チトセ
《原文》口が省略された異体字(遠)




1番の開山の年号はありませんが、二世が弘治元年(1555)とありますから、大験寺は遅くとも十六世紀前半には存在していたことになります。この時期は、宝泉寺が如幻宗悟によって開山されたとされる永正年間(1504-1521)と重なります。5番はおそらく八世と彫られていた部分が欠落していますが、銘から七世との親子関係がわかります。修験道寺院らしく歴代に大越家や大先達といった称号がみられるのも特徴的です。なお2番から4番は銘の書式や碑の形状が類似しており、1番とともに同じ時期に造られた可能性があります。
9番の英須は宝泉寺にある徳本名号塔の銘に見られる人物です。墓碑もこれだけは形式が違っているので特別な人物だったのかもしれません。11番は大験寺最後の別当とされる遠藤知英氏で、『遠藤の昔の生活』によれば大験寺廃寺とともに還俗し明治中期まで御嶽神社の神主をされたとあります。また知英氏は郷学「琢成学舎」を創設したとも伝えられています。この碑には当時の遠藤の人々の名前が刻まれており、知英氏の顕彰碑あるいは筆子碑でもあります。『茅ヶ崎市教育史』(1987 茅ヶ崎市教育委員会)には、12番の遠藤忠造氏が遠藤学校(学制頒布後の琢成学舎)で教師をされていたことがわかる明治十二年の記録が掲載されています。遠藤学校はその後小出小学校藤沢分校から藤沢市立秋葉台小学校となって現在地に移転しました。
以上を表にまとめると下記のようになります。
| 開山 | 泉蔵 | 〔記載なし〕 | |
| 二世 | 永昌 | 弘治元年(1555)七月十三日 | |
| 三世 | 昌全 | 慶長四年(1599)四月二十二日 | |
| 四世 | 春林善秋 | 寛永五年(1628)正月二十三日 | 鏡法院父 |
| 五世 | □光秋本(鏡法院?) | 万治二年(1659)三月十三日 | 乗法院父 |
| 六世 | □岳性旲(乗宝院?) | 元禄十一年(1698)十月二十三日 | 大教院父 |
| 七世 | 玄秀(大教院) | 享保三年(1718)二月二十二日 | 大乗院父 |
| 八世 | 秀全(大乗院) | 安永九年(1780)四月六日 | 九十二歳没 |
| 九世 | 教順(普門院) | 宝暦四年(1754)十月十九日 | |
| 十世 | □要(大教院) | 寛政九年(1797)十二月二十二日 | |
| ? | 〔不明〕 | 享和二年(1802)十一月三十日 | |
| ? | 英須 | 文政十年(1827)十二月十一日 | 宝泉寺徳本名号塔(1818) |
| ? | 恵雲 | 文政十二年(1829)六月三日 | |
| ? | 遠藤知英 | 明治十八年(1885)八月五日 | 郷学琢成学舎創設 |
| ? | 遠藤忠造 | 明治二十四(1891)九月六日 | 遠藤学校教師 五十二歳没 |
これ以外に銘が読み取れるもの(多くは女性の墓碑)が10基程度確認できますが、歴代との具体的なつながりを示す情報はほとんど得られません。唯一それがわかるのは下記13番の元禄十四年(1701)の墓碑で、これは全体に文字が荒く、特に左面の文字は乱れておりが読みづらいのですが、大教院下女と彫られているようです。大教院は七世と十世の二人いますが、年号からこちらの大教院は七世です。もう一基、14番にあげた天樹院□姉と刻まれている風化の進んだ寛政三年(1791)の墓碑がありますが、天樹院が誰にあたるのか不明です。
13 角柱弧頭 元禄十四(1701)
[正面]元禄十四巳天 妙白禅定尼㚑位 三月五日
[左面]大教院下女
14 角柱弧頭 寛政三(1791)
[正面]〔梵字ア〕□心院如蓮□□大姉□
[右面]寛政三辛亥天 七月……
[左面]天樹院□姉(□は間か?)
この墓域にある墓碑の配置には脈絡がなく、歴代墓碑の位置もばらばらに散らばっています。ある時期に別の場所からここに移転したか、あるいは墓域が縮小するなどの機会に墓碑の整理・移動が行われたと考えられます。その折に歴代墓碑が特段意識されたようには見えませんが、それにもかかわらずこれだけのものが銘文が読み取れる状態でよく残っていたと思います。この周辺は開発対象になっていないうえ、草木やブロック塀のおかげで風化の速度が緩和されてきたのでしょう。
最後に宝泉寺境内の徳本名号塔の銘文を示します。文政元年に建立されたこの塔は仁孝天皇即位記念碑でもあります。基礎石には近隣の15の村の念仏講中の人数が村名とともに記されておりその総数は391人、名が書かれているのも78名あり、徳本が宗派をこえて人々に受け入れられていたことがわかります。同じく基礎石に大験寺英須の銘がある経文は、万治三年(1660)に天台僧光憲によって書かれた経文集『浅学教導集』にあるもので、念仏講による造塔供養のための経文とされているものです。

[正面]南無阿弥陀仏 徳本〔印〕
[右面]今上皇帝寶祚萬々歳 大樹幕下御武運盛隆
[左面]稽首天人所恭敬 阿弥陀仙両足尊 在彼微妙安樂国 無量佛子衆圍繞
[背面]文政首年戊寅九月吉辰
[基礎正面](出典:浅学教導集巻第十一 八念仏講塔婆)
諸教所讃多在弥陀故以西方而
爲一准矣蓋以称名念仏者現受
無比楽之善因後生清淨土之津梁
越 村落老壯
尊重粛々頼無量光本願
勤厚綿々結念仏講良縁
拝瞻三諦聖容送於多念
口誦六字名号滿於數返
茲以
築毗盧遊戯黄壚致功徳樹
木供養
若尒同志壇主今世之間蒙安
富安榮祥瑞異滅後昇上品上生
廣閣 乃至
三界衆類共詣唯心淨刹
六道群機同謁已心弥陀
大験寺住
英須法印謹誌
《原文》乐(樂)羪(養)
[基礎右面]世話人 當村講中百十一人 〔二十四人名列記〕
[基礎背面]世話人 高田村三人 石川村 行谷村十人 堤村三十六人 獺郷村二十二人 打戻村二十三人 折戸村三人 赤羽村十三人 〔二十四人名列記〕
[基礎左面]世話人 寺尾村廿八人 天沼村二人 香川村十人 石川村六十三人 大庭村小糸十八人 大庭村北谷廿一人 芹沢村二十九人 〔三十人名列記〕