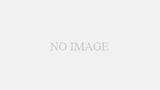藤沢市遠藤は北部のヤト(谷戸)や南西部のクボ(窪)と呼ばれる低い土地と、中部のハラ(原)と呼ばれる小高い台地の二種類の地形から成り立っており、このうちハラの地域には秋葉原・東原・向原・北原・松原・中原・南原といった原を含む地名が小字として残っています。ハラの東部や南部は昭和三十年代にはじまった都市開発によって姿が一変し、中でも北原は南の2/3が工場地帯となり、北部にかろうじて開発を免れた昔の風景が残っています。
この北原の北端に小さな共同墓地があります。『藤沢市の石仏』(2003 藤沢市教育委員会)には北原墓地と記されているこの区域は、代々この地に住む旧家の墓地です。一方ここにはどこの家の墓域にも属さない無縁墓碑数基が2か所に集めて並べられており、この中に文化七年(1810)の廻国塔が1基含まれています。写真の四基のうち一番左のものがそれで、それ以外の三基は僧侶の墓碑です。この廻国塔には以下のような銘が刻まれています。

1 角柱弧頭 文化七(1810)
[正面]天下和順 常刕多賀郡 奉納大乘妙典日本廻國 日月清明 神岡行者了西
[右面]文化七午年二月十四日
[左面]相刕高座郡 願主遠藤村中
常州多賀郡神岡とは、現在の茨城県北茨城市関本町神岡にあたります。銘からは、廻国巡礼の行者了西が遠藤村にやってきて、村の人々が願主となって了西の廻国を記念する塔を造立したと解釈できます。しかしこの廻国行者がなぜ遠藤村にやってきて、いかなる経緯で村の人々がこの塔を建立したのかは読み取れません。この北原北部は、厚木道(現在の県道藤沢・厚木線)の中村の辻(現在の一色西交差点あたり)から西に分かれて宝泉寺に向かう道沿いだったので、参詣者が通行するところではありましたが、廻国巡礼者がとどまるところにも思えません。
次に残りの三基を見てみると次のような銘が刻まれています。赤字で書いたところは風化や剥離のため読み取れず、藤沢市の文化財総合調査報告書第三集(1988)で補ったものです。廻国塔の隣にある無縫塔には了西法師と刻まれており、これは廻国塔の行者了西と同名です。残念ながらこの塔には日付が書かれていないので確かなことは言えませんが、偶然の一致ではないでしょう。なお4番の右奥に置かれているのは地蔵菩薩立像の残欠で、銘はありません。
2 無縫塔 造立年不詳
[正面]方譽了西㳒師
3 無縫塔 天明四(1784)
[正面]天明四辰年 歸元授山□字沙彌位 十月二十四日
4 角柱笠付 造立年不詳
[正面]白蓮社㳒誉浄西 大徳←
もう一か所の無縁墓域には五基の墓碑が見られます。写真右端の無縫塔の後ろに、2つに折れた墓碑が残っています。これらの銘は以下の通りです。なおこのほかに地蔵菩薩像の残欠がいくつか見られますが、これらには銘はないようなので省略しています。

5 舟型 造立年不詳
[正面]空心虚谷沙彌 歸空〔釈迦如来座像〕荘厳 八月廿五日
6 無縫塔 造立年不詳
[正面]教誉圓心
7 舟型 延宝元(1673)
[正面]歸寂妙清㚑尼 〔如意輪観音菩薩半跏思惟像〕 延宝元癸丑天霜月十日
《原文》⿱⺕⺣(㚑)
8 無縫塔 安永九(1780)
[正面]安永九庚天 ……沙弥霊位 六月二十六日
9 角柱弧頭 明和七(1770)(倒壊)
[正面]明和七寅年 圓寂夢宅槐沙弥品位 忌主 三月十□日 内田七兵衛
3番、4番、6番は僧名から浄土宗であることがわかります。他も沙弥と書かれたものが多く、かつてこのあたりに浄土宗系の寺院あるいは小堂があったと思われます。しかし遠藤に浄土宗寺院があったとの記録は知られておらず、新編相模国風土記稿(1841)にも遠藤村の寺院は曹洞宗の宝泉寺と修験道の大験寺しかあげられていません。またこの墓域に残る旧家の墓碑にも浄土宗のものはありません。ところで遠藤村にはこの他に浄土宗の僧名がみえる石碑が二基宝泉寺に残っています。写真の右二基がそれですが、左の念仏塔も同時期のものなのであわせて銘文を紹介します。

10 舟型 元禄元 (1688)
[正面]爲寒念佛法界菩提也 〔梵字阿弥陀如来 阿弥陀如来立像〕 元禄元辰十二月日同行九人
《原文》合字(菩提)
11 舟型 延宝九 (1681)
[正面](右側)延宝九辛酉十月日 遠藤村惣檀那 有縁無縁等
(中央)……日總回向〔六臂如意輪観音半跏思惟像〕
(左側)願主西譽浄圓 導師翁譽
(下部)〔法名七名〕
《原文》捴(總)
12 六面幢 元禄五 (1692)
[第一面](上部)二 (中央)一躰施主七人 〔地蔵菩薩立像(香炉)〕
(下部)〔俗名二十一名 名のみ〕
[第二面](上部)千 (中央)〔地蔵菩薩立像(合掌)〕
(下部)元禄五壬申天 法誉存知清誉浄心安誉浄□ 願主方蓮社西誉浄円大徳 方誉□西心誉浄信真誉□□ 九月十六日
[第三面](上部)日 (中央)〔地蔵菩薩立像(蓮華)〕
(下部)〔俗名二十三名 名のみ〕
[第四面](上部)惣 (中央)〔地蔵菩薩立像(錫杖・宝珠)〕
(下部)〔俗名九名 名のみ〕
[第五面](上部)回 (中央)一躰施主 〔地蔵菩薩立像(天蓋)〕 〔法名一名〕
(下部)〔法名四名〕
[第六面](上部)向 (中央)〔法名一名〕 〔地蔵菩薩立像(幢幡)〕一躰施主 助之丞 〔法名一名〕
(下部)〔俗名八名 名のみ〕
10番の念仏塔は『藤沢市文化財総合調査報告書第3集』(1988)では阿弥陀如来としていますが、梵字は釈迦如来をあらわすバクであるようにも見えます。12番の六地蔵が浮き彫りされた六面幢には二千日総回向とあり、7名の浄土宗僧を含む多数の人名が記されています。この塔の造立時には盛大な供養が行われたことでしょう。また遠藤村惣檀那と刻まれている11番は上部が欠けて読めませんがおそらく12番と同じく何千日総回向と刻まれていたのでしょう。これら二基の願主はいずれも西誉浄円という僧だったことが読み取れます。
これらの塔に刻まれた僧と北原墓地の僧との関係はわかりませんが、12番に見える方誉□西は他の僧名から類推すると方誉浄西であった可能性が高く、ひょっとするとこれは4番の法誉浄西と同一人物なのかもしれません。どのような経緯でこれらの念仏塔が宝泉寺にあるのかはわかりませんが、旧大験寺から宝泉寺に移設されたと考えられている徳本名号塔(こちらで紹介しています)のように、かつて存在した祈祷寺から移されたものなのかもしれません。いずれにしても当時の遠藤の浄土宗僧は人々の念仏信仰に深くかかわっていたことが見て取れます。
小嶋博巳氏の『六十六部日本廻国の研究』(2022 法藏館)には、「近世の六十六部は阿弥陀信仰ときわめて親和的であり(中略)当時の六十六部廻国者の中核が念仏者であった考えた方がよいレベル」とあります。北原墓地の廻国塔に見える行者了西は、念仏者のネットワークによって遠藤にやってきたのでしょうか。遠隔地の行者名が記され造立地の村中が願主となっているという、おそらく典型的とは言えないこの廻国塔から想像されるのは、この行者はしばらくの間遠藤の地に滞在し、村の人々との深いつながりができ、もしかするとここに住み着いたかのかもしれませんが、遠藤村の人々が発願して塔を建てるほどの何かがあったということです。あるいは行者がこの地で亡くなったあと、遠藤村の人々が亡き行者を供養する塔を廻国供養の塔として造立したのかもしれません。しかし造塔の経緯を裏付ける資料は残っておらず、寺院の廃絶とともに人々の記憶からも失われてしまったようです。