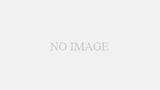藤沢市北部の中央やや西側にある菖蒲沢は東西に細長い形をしており、その東部には県道藤沢厚木線の新道が南北に走っています。この菖蒲沢大平交差点のすぐ西側に浄土宗寺院があります。正式名を仏心山清澄寺浄土院というこの寺は、鎌倉光明寺二十七世光誉西隠(二十六世や二十八世とする文献もある)によって文禄年間(1592-1596)に開山されたと伝えられています。西隠は藤沢市本町にある常光寺の開山としても知られている人物です。浄土院墓地にある菖蒲沢の旧家高橋家の墓碑のひとつには、高橋家の歴史とともに西隠が高橋家の家系に属するとする伝承が記されています。

浄土院は藤沢市の文化財にも指定されている筆子塚の存在で知られています。今に残る十一基の歴代墓碑のうち五基に筆子中あるいは惣筆子中と刻まれており、現在この五基は歴代墓域の右側に、それ以外の墓碑は左側にとわかりやすく(?)並べられています。以前はすべての墓碑が一列に並べられていましたが、平成十九年に墓域を整備した際に今のようになりました。この整備の記録は『藤沢市文化財調査報告書 第43集』(2008 藤沢市教育委員会)に詳しく書かれています。またここには藤沢市教育委員会が設置した看板が立てられており、そこには次のように書かれています。

市指定記念物(史跡)
浄土院筆子塚群五基
筆子塚とは江戸時代、寺子屋で学んだ幼童が、師の報恩のために墓碑を建て供養したものである。寺子屋教育は社会奉仕の一つであると同時に、住職の生活費にあてる目的もあったようである。江戸時代の慣習として、住職の専住は稀で転住を繰り返し、当寺で亡くなった住職のみが葬られたのである。
浄土院の歴代墓碑は九基あり、そのうちの五基が筆子塚である。古いものが輪誉(寛政九年寂、一七九七)から二十五世動誉まで約半世紀、五代にわたって寺子屋が継続されたのは珍しく、こうした事績は後世に伝えていきたいものである。
平成四年二月一日指定
藤沢市教育委員会
これら五基の銘を以下に世代順に示します。2番には何世とは刻まれていませんが、墓域右奥にある歴代墓誌に同じ没年月日をもつ人物が記されており、ここから二十一世であることがわかります。ただし墓誌にはこの人物は響譽上人と書かれており、高譽上人ではありません。また5番には没年が書かれていませんが、これも歴代墓誌に同一名の人物が見えるので、そこから明治三十九年没であることがわかります。なおこれらの墓碑は世代順には並んでおらず、奥から2,3,1,4,5の順番に配置されています。
1 無縫塔(二十世)寛政九(1797)
[基礎正面]當寺 輪譽上人 廿世
[基礎右面]寛政九丁巳天 八月二十日
[基礎左面]施主 惣筆子中
2 無縫塔(二十一世)文化八(1811)
[塔身正面]高譽上人
[基礎右面]文化八辛未年 三月六日
[基礎左面]施主 惣筆子中
3 無縫塔(二十三世)文化十四(1817)
[塔身正面]文化十四丑年 東蓮社漸譽上人頓阿大賢和尚位 三月廿日
[塔身右面]二十三世
[基礎正面]施主 筆子中
4 無縫塔(二十四世)天保十一(1840)
[基礎正面]中興 章譽上人
[基礎右面]天保十一子年 十月十五日
[基壇正面]施主 惣筆子中
5 無縫塔(二十五世)明治三十九(1906)
[基礎正面]廿五世 勲譽上人 准中興
[基壇正面]施主 惣筆子中
藤沢市内で確認されている筆子塚は25基から30基程度(何を筆子塚と呼ぶかによって総数が変わる)ありますが、どの文献をみても浄土院には5基の筆子塚があると書かれており、それらはここにあげた藤沢市の文化財に指定されているものを指しています。しかし浄土院墓地にはもう一基、恐らくまったく知られていない別の筆子塚が存在しています。それは下記に示すもので、どこの家の墓域にも含まれていない(ように見える)一画に置かれているので、無縁墓碑なのかもしれません。


6 角柱尖頭 安政三(1857)
[正面]〔梵字キリーク(阿弥陀如来)〕(右側)淨運主齢信士位(左側空白)
[右面]安政三丙辰年三月十九日 圓行村 筆子中
この墓碑の右面には筆子中と刻まれており、その点では典型的な筆子塚と言えますが、一方でかなり特徴的な筆子塚でもあります。まず、この墓碑はここから南東に1〜2kmほどの距離にある円行村の筆子中によって建てられたものであることが銘よりわかりますが、現地以外の筆子だけで造立された筆子塚はあまりないように思います。しかもこの墓碑の人物は他の五基のような住職ではなく、僧籍者でもありません。円行村出身者なのか、あるいは円行村を担当していた師匠だったのでしょうか。
さらに目を引くのが、この墓碑は未完成であるという点です。正面右側には師匠と思われる男性の法名が刻まれていますが、左側は空白です。つまりこの筆子塚は、妻の生前に夫婦墓として造られたものであり、妻が亡くなったらそこに法名が刻まれるはずだったのが、何らかの事情でそのままになり、そのうち墓自体も忘れられたということだと考えられます。その事情が何だったのかはもちろんわかりませんが、未完成の墓碑が残っているというのも珍しいことのように思います。
高田稔氏による『神奈川県の寺子屋地図』(1993 神奈川新聞社)には、現藤沢市域の江戸時代から明治初期にかけての寺子屋師匠40名が紹介されています。その後の文献『藤沢市教育史 史料編 第一巻』(1998 藤沢市教育文化センター)や『筆子塚資料集成 千葉県・群馬県・神奈川県』(2001 国立歴史民俗博物館)から知ることができる人物を含めても50名程度でしょう。記録として残っていない師匠の数ははるかに多いと考えられますから(例えば以前こちらでとりあげた遠藤旧大験寺最後の別当遠藤知英氏は教育者であった可能性が高い)、このように知られずに残っている筆子塚はまだまだあるのかもしれません。