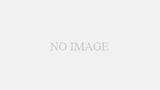小嶋博巳氏による『廻国供養塔データベース』は、全国の記録を調べあげることで一万基以上の廻国塔の情報を収集し、それを検索可能な形でデジタル化した画期的なデータベースで、こちらからダウンロードもできます。また同氏による『六十六部日本廻国の研究』(2022 法藏館)は、六十六部に関する最新の研究成果を知ることができ大変興味深いものです。このデータベースには藤沢市の廻国塔が7基収録されていますが、そのうち銘文が完全に近い形で収録されているものは2基にとどまります。
そこで、ここでは藤沢市に現存する廻国塔21基(廻国塔かどうか不明な1基を含む)をその銘文とともに紹介します。廻国塔の定義には深入りせずに廻国者に関係すると考えられる塔はすべて収録しています。表中の《文献》の項はその塔の銘文を記録した既存文献を示しており、それぞれの略号の意味は以下の通りです。現況の塔から銘文が読み取れない場合は、これらの文献の記録を参考に赤字で補っています。
文財:藤沢の文化財7-9(1963-1965 藤沢市教育委員会)
市史:藤沢市史1(1970 藤沢市役所)
総合:藤沢市文化財総合調査報告書1-9(1986-1994 藤沢市教育委員会)
石仏:藤沢市の石仏(2003 藤沢市教育委員会)
1 獺郷1589 東陽院墓地 文化二(1805) 角柱尖頭
[正面]天下和順 奉納大乗妙典六十六部供養塔 國土安全
[右面]旹文化二乙丑歳 七月吉日
[左面]……郡□田村 願主……
《原文》羪(養)
《文献》総合1,石仏
東陽院墓地の一画に地蔵菩薩塔や馬頭観音塔とともに並べられています。近隣に散在していた石碑を引き取ったのでしょう。風化が激しく肝心の左面の文字は読めそうで読めません。高座郡用田村であったかもしれません。既存文献の左面の記録は恐らく正しくないため、ここでは採用していません。
2 用田1084 西用田バス停傍 文政十(1827) 角柱尖頭
[正面]天下泰平 〔梵字アーンク〕奉納大乗妙典日本廻國供養塔 国土安全
[右面]文政十亥年九月吉日
[左面]……用田村
《原文》𭤖(政)
《文献》総合1,石仏
バス停近くの畑の中に念仏塔や巡礼塔などとともに並べられています。全部で六基あり古いものは天和三年(1683)の年号があります。かつてこのあたりに小堂があったのかもしれません。この塔は風化が激しく左面はほとんど読みとれません。既存文献によれば用田村とあったようです。
3 用田128-7 個人墓地 万治三(1660) 角柱剣頭
[正面]〔菊紋〕萬治三年六月二十九日 經雲禅定門
[右面]日本廻国成就之 願主石塚天正
[左面]三界萬霊有縁無縁 施主石塚喜左衛門
用田の旧家石塚家の墓地にあるものです。年号は古いですが塔は新しいものです。願主である廻国成就者の供養塔を施主が造立したものでしょう。この塔は既存文献には見えません。なおこのすぐ近くに安永四年(1857)の不動明王塔があり、ここにも石塚姓が刻まれています。
4 葛原1367 谷戸入口バス停傍 宝暦九(1759) 丸彫
[正面] 〔地蔵菩薩立像(錫杖・宝珠)〕
[左背面] 庭澗童子 寅九月廿八日
[基礎正面] 奉納廻國順禮供養
[基礎右面] 維時宝暦九己卯天
[基礎左面] 九月十五日 葛󠄀原邑 斉藤□十郎
《文献》総合1,石仏
バス停北の林の中に二体の地蔵菩薩立像が祀られている小堂があり、その右側のものです。廻国順礼とある基礎石には宝暦九年と刻まれていますが、地蔵像にはそのちょうど一年前と思われる日付が彫られています。斉藤氏は葛原の旧家です。銘からは廻国者が誰だったのかははっきりしません。
5 葛原2544 個人墓地 年代不明 角柱弧頭
[正面]…… ……大乗妙典六拾六部供養 ……月吉祥日
[右面]右ほしのやみち 左大山道
[左面]願主淨心
葛原の旧家矢部家の墓地にあるもので、正面は崩落しており、散乱する断片からかろうじて廻国塔であることが知られます。これは道標でもありますが、この墓地前の道はかつて星の谷道と呼ばれた旧道ですので、昔はすぐ近くの辻に置かれていたのでしょう。この塔は既存文献には見えません。
6 遠藤2253 北原墓地 文化七(1810) 角柱弧頭
[正面]天下和順 常刕多賀郡 奉納大乗妙典日本廻國 日月清明 神岡村行者了西
[右面]文化七午年二月十四日
[左面]相刕高座郡 願主遠藤村中
《文献》総合3,石仏
これは以前こちらで紹介したものです。記録には残っていませんが、昔このあたりに浄土宗寺院あるいは念仏堂があったと思われます。この塔のすぐ隣に、年号はないものの了西法師と刻まれた無縫塔があり、遠方からやってきた行者了西はここ遠藤で亡くなったようです。
7 下土棚999 善然寺墓地 天明元(1781) 角柱孤頭
[正面]日本回國供養塔
[右面]天明元辛丑年 五月十二日
[左面]願主 棋誉住心 敬白
用田バイパスをはさんで善然寺の北側にある墓地の一画、下土棚村の旧家小菅家の墓域の中にあるものです。小菅家は善然寺とゆかりが深く、善然寺の僧籍をもつ小菅家の棋誉が廻国巡礼を成就させたのでしょう。この塔は既存文献には見えません。
8 高倉258 東勝寺前 寛政九(1797) 角柱尖頭
[正面]奉廻國大乗妙典供養塔
[右面]維持寛政九龍舎丁巳初冬如意珠日 點燈山東勝禅寺現住昌泉謹誌
[左面]相模州高座郡七次郷願主了参
《原文》羪(養)
《文献》総合2,石仏
東勝寺門前の駐車場の端にあります。台石は平成になって造られたもので、現在は見上げるほど立派な塔になっています。願主の了参は、近くの境川の氾濫で亡くなった方の供養のために廻国奉経の旅に出たと伝えられています。かつて境川は川筋が変わる程の氾濫を繰り返していました。
9 亀井野1457 雲昌寺 宝暦十四(1764) 宝塔類型
[塔身](正面)佛(背面)法(右面)僧(左面)〔烏八臼〕
[基礎正面]六十六部 奉納大乗妙典 供養之塔
[基礎背面]宝暦十四甲申天四月 當寺十世本苗和尚第子 幡州□□郡□□村 願主浄全 當山十一世現住本英叟代
[基礎右面]願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆倶成佛道
[基礎左面](十五名法名読取困難)
《文献》文財9、市史1,総合3,石仏
雲昌寺門前にある多宝塔に似た様式をもつ塔です。風化剥離が著しく銘文は読み取れないところが多いものの、雲昌寺十世天山本苗の弟子である浄全が廻国者だったことがわかります。この塔は大変立派なもので廻国供養はさぞかし盛大だったと思われますが、廻国の目的は何だったのでしょうか。
10 善行2-19-8 善行神社 宝暦三(1753) 丸彫
[正面]〔大日如来座像(智拳印)?〕
[基礎正面]大乗妙典六十六部
[基礎右面]相州高座郡善行寺村 願主悟州□了庵主
[基礎左面]維時宝暦三癸酉歳 十二月吉祥日造立之
《文献》総合8,石仏
善行神社内に集められている多数の石碑のひとつです。風化が激しく銘文はかろうじて読み取れる状態ですので願主名は誤っているかもしれません。善行寺は江戸時代にあったとされる寺院で村名にもなっていますが、資料が残っておらず詳しいことはわかりません。小堂だったのかもしれません。
11 立石3-3182 立石神社 安永二(1810) 角柱
[正面]〔大日如来座像(智拳印)〕……供養
[右面]安永二巳三月日
《文献》総合8,石仏
立石神社内に多数並べられている石碑のひとつです。既存文献には廻国塔とあったので収録しましたが銘文は風化のためそのことは読み取れません。六十六部あるいは廻国と彫られていたのかもしれませんが、既存文献にはそれとわかる銘は記録されておらず、これを廻国塔とした根拠が不明です。
12 西富1-8-1 清浄光寺 正徳四(1714) 角柱孤頭
[正面]天下太平 覺翁了圓|妙證禪定尼 奉供養大乘妙典六十六部願成就處 國土安全 正德四甲午年 四月二日
[正面下部]願主 運譽故心
[右面](上段)林譽貞廊 春譽淨薫 妙光比丘尼(中段)月窓浄因 心譽妙傳 玉雲元光(下段)関窓妙三大姉 雲叟道外信士 喜菴道意信士
[左面](上段)芳林童女 元明童女 花光童女(中段)浄雲信士 如弌境心信女 月窓哲秋信士(下段)浄徳元照信女 來空道木信士 花窓貞春大姉
《文献》総合9,石仏
清浄光寺境内の俣野大権現社付近の石塔群にあるものです。成就處とあり、運譽故心の廻国成就を記念したものであることがわかります。この塔には正面と左右面に20名の法名が刻まれています。廻国の目的は不明ですが先祖供養だったのかもしれません。正面に記されている男女は両親でしょうか。
13 藤沢695 金砂山観音堂 年代不明 角柱孤頭
[正面]〔梵字阿弥陀三尊〕天下太……… 六十六部供養 国土安全 願主教蓮社隨誉法順
[左面]光誉浄清士 窓誉香顔女
《文献》総合8,石仏
金砂山観音堂境内に並べられている石塔のひとつです。右面が損傷しており造立年代は不明ですが平野雅道氏によれば、藤沢の常光寺の過去帳に「延宝三年十二月三日 隨誉法順比丘 山城洛陽之道心者」とあるとのことです(『 藤沢市文化財調査報告書 第59集』2024年)。現在知られている廻国塔のほとんどは1700年以降のものなので延宝三年(1675)というのはかなり古いといえます。左面に法名が書かれた男女と願主との関係は不明です。
14 渡内1-1-1 天嶽院墓地 宝暦四(1754) 角柱笠付
[正面]手引地蔵菩薩 六十六部供養 願主 大和國南都信順|武蔵國浄休
[右面]六道四生有縁無縁 三界萬靈平等利益 天嶽十四世悟國叟代
[左面]于時宝暦四甲戌 九月
《原文》𭴾(無)
《文献》総合7,石仏
天嶽院墓地の無縁墓域に集められた石塔群の中にあります。願主名にある都という文字は左下の「日」が「口」になっており部のように見えなくもありません。大和国と武蔵国の二人の願主がどのような関係をもつ人物で天嶽院とどのようなつながりがあったかは不明です。
15 鵠沼神明3-4-37 万福寺 安永四(1775) 角柱
[正面]奉納大乗妙典六十六部供養塔
[右面]安永四乙未年十月吉日
[左面]相州高座郡藤沢町 行者沼田清兵衛 生國三浦
《原文》𫝶(座)
《文献》文財9,総合5,石仏
万福寺の西門外に庚申塔二基とともに並べられています。この行者がどのような人物だったかわかっていません。『藤沢の文化財9』ではこの塔は、現在も多数の塔が置かれている大鋸2丁目の堰跡橋近くの川沿いにあったとされ、この記述が正しければそこから移設されたことになります。
16 鵠沼神明495-1 鵠沼墓地 安永三(1774) 角柱孤頭
[正面]〔梵字阿弥陀三尊〕天下泰平 奉納大乗妙典六十六部供養塔 國土安全
[右面]安永三甲午十月吉日
[左面]願主淨心
《文献》総合5
万福寺北の鵠沼墓地内の一画、鵠沼の旧家渡辺家の墓域にあります。本鵠沼の普門寺に残る納経帳や木札から、この廻国者浄心とは渡辺万右衛門という人物で明和六年(1769)に二十一国を訪ねたことがわかっています。このようなコンパクトな廻国も少なくなかったようです。
17 辻堂元町3-15-13 寶泉寺 寛保二(1742) 角柱尖頭
[正面]〔梵字アビラウンケン〕常光明真言
[右面]辻堂村 寛保二壬戌三月二十一日
[左面]日本廻國六十六部四國沙門願主空山
《文献》文財7,市史1,総合5、石仏
かつて大山詣の帰りに参詣する寺として賑わったとされる寶泉寺は光明真言道場とも呼ばれていました。ここには多くの石塔が集められており、そのうちの一基がこの光明真言塔です。空山という廻国聖が建立したと読み取れます。この塔の再建と考えられる文化六年(1809)の塔が2基残っています。
18 辻堂元町3-15-13 寶泉寺 文化六(1809) 角柱尖頭
[正面]〔梵字光明真言曼荼羅〕寛保二壬戌天辻堂村海龍山堂場 常光明真言江之道 三月廿一日願主四國伊豫之沙門空山敬白
[右面]從是南江入本堂マテ八丁
[左面]于時文化六己巳天八月廿一日再興 現住祐寂代
《原文》𭏍(場)
《文献》文財7,市史1,総合5、石仏
寛保二年塔のすぐ手前にあります。この塔の再建と考えられますが、こちらは道標でもあり銘文もずいぶん違っています。あるいはこの塔の元となった空山による別の寛保二年塔があったのかもしれません。この塔の銘文には廻国や六十六部とはありませんが、元の塔との関係で収録しました。
19 辻堂神台2-13-24 大山街道入口交差点 文化六(1809) 角柱尖頭
[正面]〔梵字光明真言曼荼羅〕常光明真言
[右面]寛保二壬戌之三月廿一日 願主豫州沙門空山 辻堂村寶泉寺
[左面]于時文化六己巳之八月日再興
《文献》文財7,市史1,総合5、石仏
これも寛保二年塔の再建と考えられるものですが、こちらは光明真言塔ですので形式は元の塔に近いものです。風化が激しく、表面から剥がれ落ちた破片からかろうじて銘文の一部が読める状態です。この塔の銘文にも廻国や六十六部とはありませんが、元の塔との関係で収録しました。
20 鵠沼石上1-11 砥上公園 延享三(1746) 角柱
[正面]〔梵字阿弥陀三尊〕相州高座郡…… 六十六部…… 願主……
[右面]延享三丙寅天二月吉祥日
[左面]右ふしさわ遊行はし
《文献》市史1、総合5
砥上公園に集められた庚申塔や道祖神塔などとともに並べられています。著しく風化が進んでおり、かろうじて正面上部の梵字と右面の年号の一部が読める状態です。願主はわかりません。この塔は道標でもあったようです。
21 江の島2-3-21 中津宮 天保十二(1841) 自然
[正面]龍眠書〔印〕〔印〕 石工宮龜年 江戸小網町
いさここに とまりて きかんほとときす 古帳庵
ふた親に みせたしかつお 生てゐる 古帳女
[背面]天保十二年 龍集辛丑夏六月 日本回国六十六部 江戸小網町 鈴木金兵衛 当所世話人 橘屋武兵衛|堺屋彦兵衛
《文献》市史1、総合7
江の島中津宮の社殿左の庭園にある句碑です。古帳庵は本名を鈴木金兵衛(1781-1859)という江戸の豪商で、夫婦で全国六十六カ国の霊場を廻り納経の旅をしました。この塔は廻国成就のあとに各地で作られたものです。鈴木金兵衛の生涯については『古帳庵鈴木金兵衛をめぐって』(1994 越生町教育委員会)に詳しく書かれています。
これら21基のうち、廻国塔かどうか不明な一基(11番)および廻国そのものが造塔の趣旨ではないもの、すなわち正面に廻国あるいは六十六部の文字がない五基(3,17,18,19,21番)を除いた15基が本来の意味での廻国供養塔にあたります。そのうち願主あるいは行者名が読み取れるものが12基あります。これらの多くは村を出発した廻国者が巡礼の旅を終えて出発地に戻って造立されたと思われますが、中には村にやってきた廻国者によってあるいは村にやってきた廻国者のために造立されたものもあるでしょう。銘文だけから廻国の目的や造塔の経緯を推定するのは多くの場合困難で確かなことは言えませんが、例えば6番と14番は後者と考えられます。

遠藤北原墓地にある6番は以前に紹介しました。渡内天嶽院にある14番は密集した無縁墓石群の中に置かれており、天嶽院十四世の名が刻まれているものの忘れられた状態にあります。なお十四世悟国の名は天嶽院境内にある明和元年(1764)の地蔵菩薩塔にも見ることができます。この廻国塔には手引地蔵との銘があるものの地蔵像はなく現状は笠付の文字塔ですが、最初からこの形式だったのかどうかわかりません。地蔵像が付いていてもおかしくない塔だと思います。
銘からはこの廻国塔の願主は大和国南都信順(あるいは大和国南部信順)と武蔵国浄休の二名のように読み取れますが、二人は一緒に廻国巡礼をしていたのでしょうか。この塔は巡礼の途中で天嶽院にしばらくとどまった折に造られたものでしょうか。この二人は天嶽院とどのような関係があったのでしょうか。手引地蔵はあまり一般的な地蔵ではなさそうですが(おそらく藤沢市で手引地蔵の銘のある石塔はこれだけ)、これは巡礼の安全祈願と関係があったのかあるいはこの二人が巡礼中に出会ったことを象徴しているのでしょうか。疑問は数々あれど、残念ながら手掛かりはありません。