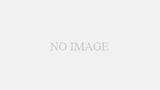藤沢市中央西部に広がる大庭は長い歴史を持つ地名で、平安時代に書かれた書物にもその名が現れます。その中央部には平安時代末期に大庭景親が居城していたとの伝説がある大庭城がありましたが、戦国時代に廃城となり現在は大庭城址公園として保存されています。大庭は昭和三十年代に始まった大規模な開発で宅地化が進みその姿は一変しましたが、その東部を南北に流れる引地川東岸の山すそには昔の姿が残っています。ここに延喜式内社の旧跡とも伝えられる大庭神社と、十四世紀に創建されたとされる真言宗寺院の成就院があります。江戸時代成就院は大庭神社の別当寺でした。

成就院の墓地にはたくさんの石塔がきれいに並べられている一角があります。コンクリートで固められた集積塔の四面二段に24基、集積塔の頂上に1基、その右側と左側にそれぞれ5基の合計35基の石塔がそこにはあります。時代は寛文十年(1670)から天保五年(1834)にわたります。『藤沢市の石仏』(2003)を見ると以前は35基全部が1つの集積塔となっていたようですが、その後今の形に整理しなおされたようです。このうち約半分は法名が刻まれた通常の墓碑ですが、それ以外にさまざまな神仏像が彫られた石塔があり、数えてみると15尊にのぼります。そのうちいくつかは同一人物により造立奉納されたものだと考えらえれるため、以下では造立者の情報もあわせてこれらの神仏像を紹介します。

最初のグループは祐海という人物による八基で、文政十三年(1830)から天保五年(1835)までの銘があるものです。角のとれた四角形の石に半肉彫りされているのが特徴で、ほとんどのものには尊名と祐海の名が刻まれています。3番と8番は破損のため祐海名が読み取れませんが、形式からこれも祐海による同時期のものだと判断して加えています。歴代墓域に「法師祐海不生位」と刻まれた立派な五輪塔が残っているので、祐海は成就院の住職だったのでしょう。
このうち薬師如来像には本尊と記されています。しかし成就院の本尊は愛染明王で、『新編相模国風土記』(1841)にもそのように書かれおり薬師如来ではありません。これはおそらく城南にある養命寺の本尊薬師如来を示しています。像容が類似しています。養命寺の本尊である木造薬師如来座像は建久8年(1197年)の銘をもち養命寺の歴史より古く、かつて大庭城に存在した薬師堂にあったものと考えられています。『新編相模国風土記』によればこの薬師如来は霊験あらたかだったようで、当時から篤く信仰されていたことがうかがわれます。祐海はこの薬師如来をモデルとして、他の神仏像も造っていったように思われます。
なお成就院には別の木造薬師如来立像があり、『藤沢市文化財総合調査報告書第2集』(1987)によれば室町時代前期、15世紀頃の作と推定されています。『藤沢の武士と城 』(1979)によればこれも大庭城近くの祠から移されたものですが、この祠は大庭城の薬師堂とは別のもののようです。








1 薬師如来 文政十三(1830) (集積塔正面下)
[正面]本尊薬師如来 〔薬師如来座像(薬壺)〕 文政十三寅十一月祐海
2 大日如来 天保二(1831) (集積塔正面下)
[正面]金剛界大日如来 〔金剛界大日如来座像(智拳印)〕 天保二夘九月祐海
3 弥勒菩薩 年不詳 (集積塔正面下)
[正面]弥勒尊 〔弥勒菩薩座像(宝塔)〕 (破損銘欠)
4 阿弥陀如来 天保二(1831) (集積塔正面下)
[正面]阿弥陀如来 〔阿弥陀如来座像(上品印)〕 天保二夘六月祐海
5 阿閦如来 天保二(1831) (集積塔右面下)
[正面]阿閦如来 〔阿閦如来座像(降魔印)〕 天保二夘六月祐海
6 釈迦如来 天保二(1831) (集積塔左面下)
[正面]釈迦牟尼佛 〔釈迦如来座像(施無畏与願印)〕 天保二□六月祐海
7 弁才天 天保二(1831) (右側前列)
[正面]〔八臂弁才天座像〕
[左面]天保二夘五月 祐海
8 水天 天保五(1834) (左側前列)
[正面]〔梵字バン〕水天 〔水天立像(剣)〕 天保五午六月(以下破損)
次のグループは七観音として奉納されたと考えられるもので、現在確認できるのは五体(千手観音・馬頭観音・不空羂索観音・聖観音・十一面観音)です。このうち聖観音像に銘があることは知られていないようですが、そこには諏訪部甚衛門の妻が二世安楽のために七観音を造立奉納したと記されています。諏訪部は大庭領主の姓です。『新編相模国風土記』(1830)によれば江戸時代を通して大庭は数名に分給されており、成就院のあたりは諏訪部本家と諏訪家分家の領地が混在していました。
『寛政重修諸家譜』(1812)を見ると諏訪部氏には長衛門と推定される人物が一名存在します。それは本家筋の諏訪部久安(1692-1722)で、そこには次のように記されています「長次郎 長右衛門 母は某氏 宝永三年五月十五日はじめて常憲院殿に拝謁す 六年四月六日大番となり 享保七年四月五日番を辞し 十月二十四日父にさきだちて死す 年三十一 法名現霜」。そして久安の子の定救の項には「(略)享保十三年十月九日祖父の家を継(略)安永元年十一月六日死す 年六十一 法名長童」とありますので、久安は父の家督相続前に亡くなりその子の定救が十七歳で家を継いだことがわかります。
そしてもう一体、これら五体と形式が非常に似ている享保五年(1720)銘の観音菩薩塔があり、ここには「為永壽院現當安全也」と刻まれています。永寿院が誰かは不明なのでこの塔と七観音との関係はわかりませんが、久安が亡くなる二年前の年号があることから、もしかするとこれは七観音のひとつで准胝観音なのかもしれません。以前紹介した江の島延命寺の六観音(こちら)の准胝観音も二臂合掌でしたし、聖観音の右手が与願印で左手が蓮花という像容も延命寺の六観音と同じです。そうでなくても永寿院が諏訪部氏の誰かを指している可能性はありそうです。






9 千手観音菩薩 年不詳(集積塔右面上)
[正面]〔十臂千手観音菩薩立像〕
10 馬頭観音菩薩 年不詳 (集積塔右面上)
[正面]〔八臂馬頭観音菩薩立像〕
11 不空羂索観音菩薩 年不詳 (集積塔背面上)
[正面]〔六臂不空羂索観音菩薩立像〕
12 十一面観音菩薩 年不詳 (左側後列)
[正面]〔十一面観音菩薩立像〕
13 聖観音菩薩 年不詳 (集積塔左面上)
[正面]奉立七観音為二世案樂也 〔聖観音菩薩立像〕 施主諏訪部長衛門妻
14 准胝観音菩薩?/聖観音菩薩 享保五(1720)(左側後列)
[正面]為永壽院現當安全也 〔准胝あるいは聖観音菩薩立像〕 旹享保五庚子天十二月吉辰
またこの石塔群には他に丸彫りの地蔵菩薩が二基残っており、これらも墓碑ではないものです。ひとつは集積塔の右側中列にあるもので、六地蔵と刻まれていますがこの一体しか残っていません。造立主はおそらく旭元で、大庭神社にかつて存在した享保二年(1717)の梵鐘の銘文に登場する人物です。歴代墓域に「中興法印阿闍梨旭元」と書かれた無縫塔が残っています。そしてもう一基は集積塔の頂上にあるもので、これは念仏講により造立された地蔵念仏塔です。いずれも18世紀はじめもので、久安存命の時代と重なります。
15 地蔵菩薩 享保四(1719)(右側中列)
[正面]奉納六地蔵大菩薩 〔地蔵菩薩立像(合掌)〕 為二世安楽也 □□□□
[背面]稲荷山 于時享保四己亥□□ 法印旭□
16 地蔵菩薩 宝永三(1706)(集積塔頂上)
[正面]〔地蔵菩薩立像(錫杖・宝珠)〕
[背面]宝永三丙戌年 同行 奉造立念佛講供養所 二月十四日 十四人
ここに集められている石塔群は、祐海による19世紀前半のもの(1830年から1834年)を除くとほとんどすべてが18世紀前半以前の銘をもつもので(石川村の銘がある一基以外は1680年から1736年)、祐海の時代とは百年の隔りがあります。また墓碑のうち法名から成人男性とわかるものは7基ありそのうち4基が僧籍者ですので、この石塔群はかつて存在していた古い歴代墓域にあったもののようです。久安が亡くなったころ七観音はそこに整然と並んでいたはずで、それから百年後祐海の神仏像は再び人目をひく存在になっていたことでしょう。しかしその後天保年間中に成就院はに火災にあいそれまでの記録がすべて失われてしまいます。火災で墓域も影響を受けたかもしれません。そしていつしか元の姿が忘れられ、散逸が進んだ結果今の姿に整理しなおされたのだと思われます。