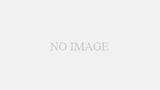藤沢市の南は海に面しています。その海岸線は5キロメートル程度なので長いというほどではありませんが、明治時代に別荘地として開発された鵠沼海岸は江の島とともに藤沢市のシンボルと言ってよいでしょう。長い歴史を持つ江の島に対して鵠沼海岸は明治初期まで砂と松以外何もないところでしたが、今やリゾート地として全国的に知られるようになりました。しかし海があるということは水の事故もあるということです。大正十二年の関東大震災では藤沢でも150人以上が津波で行方不明になりました。また中華人民共和国の国歌「義勇行進曲」を作曲した聶耳(ニエアル)(1912-1935)が昭和十年に若くして亡くなったのも鵠沼の海でした。現在鵠沼海岸の引地川東岸には日中友好のシンボルとして聶耳記念広場が作られています。
この記念広場から国道134号線沿いに400メートルほど西に行くと、道路北側に「溺死諸精霊」と記された石碑が立っています。昔はもう少し北にあったと言われていますが、いずれにしてもこのあたりはかつてほとんど何もなかったところです。この塔には明治五年の日付が刻まれているだけで、どのような事件あるいは事故があったのか銘だけからではわかりません。明治五年と言えばまだ地方の生活は江戸時代と大して変わっていなかった頃です。台石には鵠沼村とありますから、村として溺死者を弔ったものと考えられます。
1 鵠沼海岸4-6-11 竜宮橋入口交差点 角柱尖頭 明治五(1872)
[正面]明治第五壬申 溺死諸精靈 七月二十二日
[基礎正面]鵠沼村←
《原文》𭭾(死)霛(靈)
またこの塔とまったく同一の日付をもつ別の海難者供養塔が、鵠沼神明にある浄土真宗寺院万福寺に残されています。山門をくぐってすぐ左側の無縁墓域と思われるところにあります。そこには海で亡くなったと思われる六名の人物の法名と俗名が刻まれています。浄土真宗式の法名ですので、この寺で法名が授けられ供養が営まれたのでしょう。六名のうち五名は船乗りですが一名は三浦郡菊名村法昌寺住職とあります。この寺は現存しています。また左面に尾張国和田郡小鈴谷村とあるのは、水難にあったのはこの村の船だったということでしょう。正しくは知多郡小鈴谷村ですが、この村は現在の愛知県常滑市南部と美浜町北部に相当する位置にありました。
2 鵠沼神明3-4-37 万福寺墓地 角柱重頭 明治五(1872)
[正面]囧心院釋周善法師 相州三浦郡菊名村法昌寺住職|釋誠實信士 水主俗名十兵衛|釋明了信士 同亀太郎|釋順誓信士 同浅次郎|釋執持信士 同安吉|釋等生信士 同為吉
[右面]明治五年壬申年七月廿二日 於當浦海死精霊
[左面]尾張國和田郡小鈴谷村
そしてもう一基、日付は若干異なっているのですが、おそらく同じ海難による犠牲者の墓碑が辻堂元町の真言宗寺院宝珠寺の無縁墓域に眠っています。階段状に並べられた無縁塔群の一番上の左側にそれはあります。この墓石の存在はおそらく全く知られていないと思いますが、ここには尾州多屋村難破船米福丸と船の名称まで書かれています。多屋村は現在の愛知県常滑市の中北部に相当し、小鈴谷村の10キロメートルほど北に位置していました。この塔の正面には消されたと思われる法名の一部が確認できるので、別の墓碑を流用して造られたと思われます。右面には四名の法名とともに、当時の辻堂の旧家の人物四名が施主として記されています。
3 辻堂元町2-4-27 宝珠寺墓地 角柱重塔 明治五(1872)
[正面]尾州多屋村 難破船米福丸船員之墓
[右面](上段)明治五年 七月廿八日
(中段)善了信士 阿速信士 □證信士 浄現信士
(下部)施主桜井小右ヱ門 仝相沢浅右ヱ門 仝吉田八左ヱ門 仝門倉与治右ヱ門



この海難の記録としては、昭和初期に藤沢町会議員をつとめていた加藤徳右衛門氏による『現在の藤澤』(1933,『藤沢郷土史』として1980年復刊)に、明治五年七月二十七日に「暴風来襲し、鵠沼沖で難破船四艘、溺死者十人」と書かれています。この日付は供養塔のものとは若干のずれがありますが、万福寺と宝珠寺の塔に法名が記された人物は合計十名ですから数は一致しています。そこでこの暴風に関する当時の記録がないか調べてみたところ、日本初の日刊新聞とされる横浜毎日新聞(明治三年創刊)の明治五年七月、八月の記事の中にありました。以下この暴風と海難に関する記事を取り出してみます。
明治五年七月二十五日
相州江の島近くへ上総房州邉船の由にて七八
百石積以下の船三艘多分に塩積込碇泊の處去
る廿二日の暴風雨にて激浪の爲に破碎におよ
ひ乗込三十人余の内漸六人程助り二十人余は
溺死の由江の島最寄海辺へ右三艘破碎の船具
積荷等打上け殆と山の如く漸く往來致すよし
なり海邊の家屋中には吹倒候塲所も有之由な
れとも田畑には少しも害なく昨年にも勝る豊
年といふ
明治五年七月三十日
當申七月廿二日昼頃ゟ大風雨吹發り同夜第十
字頃に至り相止其節相州鎌倉郡江の嶋東浦大
破損潰家都て二十軒同所横西通り二軒洪浪海
岸へ打上け漁船大小共十三艘破壊相成豆州宇
佐美村六右衛門持押送り舩乗組〆六人の中存
亡不相分者二人怪我一人有之候
一五大力船 一艘 一千石以上の船 一艘
一千石以下 一艘
一千二十石積一艘
此舩中殊に死亡怪我人荷物流出多く金貨紙
幣共〆八百四十両余錢二十五貫文程流出
右舩々乗組人の中死亡怪我人積荷共流出許多
にして巨細取調名前書等は追て出すべく今茲
に大畧を記す者也
明治五年八月十四日
七月廿二日暴風雨にて相州江嶋に滯泊の船破沉し
乘組のもの三十人餘溺死したる追善の爲め藤澤驛
稲元屋某蔦屋某なるもの兼て日蓮宗信仰のものに
て講中を集め片瀬龍口寺の僧徒を請し七里濵にて
施餓鬼を修行し種々飾物等美を盡し同志の者數人
群集し題目の聲殆天地に響きたりとのよし四海は
皆兄弟親族ならずとも非命の死を吊ふ志は人情の
厚き殊勝なる亊實に感すへし
釋に曰亡者の爲に日蓮宗の施餓鬼となせしはむ
べなるかな祖師も一天四海皆歸妙法と説しとか
や實に溺死者其功德によりて波上に浮ひたりと
そ思ふ
この新聞に書かれた天候記録をたどると、暴風雨は七月二十二日だけでその前後は晴れの日が続いているので鵠沼沖での事故は七月二十二日で間違いないでしょう。記事にあるように江の島周辺の海域で何艘かの船が難破しており、犠牲者は近隣の村々の寺院で供養が行われたようです。八月十四日の記事にある稲元屋は藤沢宿有数の名家で明治天皇行幸の際の宿泊所にもなりました。また蔦屋は代々旅籠を経営していた旧家です。万福寺と宝珠寺の塔に記された難破船は、当時太平洋側で船団を組み港々で商品売買を行い莫大な利益をあげていた尾州廻船であったと思われます。当時江の島西浦には大型船のための停泊場があり、そこから片瀬の港までは小型船で荷物を運搬していました。難破した船はここに立ち寄ったときに暴風雨に巻き込まれたのでしょう。
ところでこの横浜毎日新聞は明治初期の世相を知る貴重な情報源です。このころは4ページもので貿易や相場に関する記事が中心なのですが、最後のページには衆目を集めそうな事件や事故の顛末といった三面記事的な話題とともに読者からの投書も取り上げられており、その論調は当時としてはかなり進歩的だと思います。この暴風と海難の記事もすべて最終ページに記されていたものです。また同時期に江の島の神仏分離後の状況が垣間見られる記事があるなど非常に興味深いものがあります。これについては別の機会にとりあげてみたいと思います。