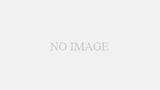今回が最後となる第四回では、海に面した三つの地域の馬頭観音塔をとりあげます。これで藤沢市内のすべての馬頭観音塔を失われたものも含めて示しました。合計すると現在までに存在を確認した藤沢市内の馬頭観音塔は154基(表のS,A,B,C)、確認できないもの(表のX)は26基となりました。確認できないもののうち10基程度は比較的最近まで存在していたものなので、どこかに移されて残っている可能性があると思います。ここで154基を造立年(正確には塔や台石に刻まれた年)ならびにいくつかの指標で分類してみます。
| 造立年 | 総塔数 | 像塔数 | 観音信仰 | 非個人 | 名なし |
| 1651-1700 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1701-1750 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1751-1800 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1801-1850 | 22 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| 1851-1900 | 37 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 1901-1950 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1951-2000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 造立年不明 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 合計 | 154 | 21 | 6 | 24 | 18 |
これを見ると馬頭観音塔は1800年ごろから急に造立されるようになったことがわかります。1751年から1800年に造立された5基のうち3基は1798年以降ですので、それ以前にはほとんどなかったことになります。像塔は全体に少なく見えますが、1841年までに限れば全体の6割は像塔で、それ以降の像塔は今に至るまで2基だけなので、突然造られなくなったように見えます。したがって造立年がわからない5基の像塔はどれも1800年代前半以前のものなのでしょう。
本来の観音信仰である、人々の救済を祈願する馬頭観音塔は数としてはきわめて少なく、江の島の2つの六観音・大庭成就院の七観音・村岡東の三界万霊塔・辻堂宝珠寺の供養塔の5基だけで(龍口寺の現代の故人供養塔1基を除く)、これらはすべて像塔です。このような馬頭観音塔は古いものが多いのですが、個々の塔の造立目的を像容や刻まれた銘文から知ることは容易ではなく、実際にはこれら5基以外にもあるかもしれません。
また個人の造立ではないと考えられるものが24基あり、その中には馬持と書かれているものや村名だけがあるもの、また複数の人名が列挙されているものなどがあります。その多くは馬持による造立と思われますが、造立目的が死馬の供養か人馬の安全祈願かは多くの場合明確にはわかりません。馬捨塚と書かれた柄沢隆昌院の塔は例外的と言えます。なお造立者に関する情報が刻まれていない塔が18基ありますが、風化により銘が読めなくなったものや失われた台石に名があったものが含まれている可能性があり、実際にはより少ないと思われます。
【8.辻堂地域(羽鳥村、辻堂村)】
辻堂地域は、現在の地名に辻堂の名が付く地域ならびに羽鳥におよそ相当します。辻堂元町はかつての辻堂村の中心部であり、いまも古い町並みの名残を随所に残しています。ここに見られる馬頭観音塔の多くは小型の文字塔ですが、宝珠寺の丸彫り像は造形的にも興味深いものがあります。また数年前まで現地にあったことが確認できる寛政四年塔は、おそらく別の場所に移されたと思われますが、今のところ移転先は不明です。
| 羽鳥3-8-6傍 | 路傍 | 同所に道祖神あり | ||
| 8-1 | A字集弧 | 昭和三十九 (1964) | 「羽鳥土地改良区之建」再建塔か | 総4, 石, M |
| 羽鳥4-3 西側 | 共同墓地 | |||
| 8-2 | A字個駒 | 嘉永四 (1851) | 石, M | |
| 8-3 | A字個尖 | 年なし | 石, M | |
| 羽鳥4-5-6 | 個人邸内 | |||
| 8-4 | A字個自 | 大正十一 (1922) | ||
| 羽鳥4-10 北側 | 共同墓地 | |||
| 8-5 | A字個駒 | 年なし | 総4, 石, M | |
| 羽鳥4-11-14 | ||||
| ー | X字個尖 | 昭和十八 (1943) | 「フリンクル号鹿毛」現地になし | 総4 |
| 辻堂1-10 東側 | 熊の森権現 | |||
| 8-6 | A字個弧 | 大正十五 (1926) | 資, 総5, 石, T | |
| 辻堂1-15 東端 | 共同墓地 | |||
| 8-7 | A字個尖 | 明治十九 (1886) | T | |
| 辻堂元町2-4-27 | 宝珠寺 | 多数の石碑が集められている | ||
| 8-8 | S像個丸 | 文化二 (1805) ? | 八臂座像 台石に童子の法名あり [総5] は元の台石ではないとする | 総5, 石, T |
| 辻堂元町3-6 南側 | 旧阿弥陀堂 墓地 | |||
| 8-9 | A字個駒 | 大正三 (1914) | 個人墓域にあり「三頭の馬頭」 | |
| 辻堂元町3-10-4傍 | 辻 | |||
| 8-10 | A字個弧 | 昭和四 (1929) | 西町馬頭観音と呼ばれているもの | 資, 総5, 石, T |
| 辻堂元町3-17-14 | 個人邸内 | |||
| 8-11 | A字個弧 | 安政二 (1855) | 史, 総5, 石, T | |
| 辻堂元町3-18-19傍 | 路傍 | |||
| ー | X字無弧 | 寛政四 (1792) | 現在所在不明 [注1] | 史, 総5, 石, T |
| 辻堂字出口 | 出口の辻 | |||
| ー | X字個柱 | 明治十五 (1882) | [注2] | 資 |
[注1] 2016年ごろまで現地にあったことが Google Street で確認できる 銘未確認
[注2] 『藤沢の文化財第七集』(1963 藤沢市教育委員会)によればこの塔は (8-11) と同じところにあった


上の左右の写真は宝珠寺境内に並べられている十数基の石塔のうちのひとつで、市内唯一の丸彫りの馬頭観音塔です。翼のように見えるところに四手、その下に二手が見えます。台石に童子の法名が刻まれていますが、同種の四つの台石のひとつに三界万霊とあるので、そちらが本来の台石だった可能性があります。年号はありませんが別の台石に文化二(1805)とあるのでその頃のものかもしれません。台石はどれも風化が進んでおり文字は読みづらいですが、過去の文献なども参照するとこれらは吽染という人物が願主のようです。
8-8 辻堂元町2-4-7 宝珠寺境内 丸彫 造立年不詳
[正面]〔八臂馬頭観音座像〕
[基礎正面]施主 爲輪照童子菩提也 ……
[別塔の基礎正面]施主 爲三界萬靈也 吽染
《原文》合字(菩提)
【9.鵠沼地域(鵠沼村)】
鵠沼地域は、現在の地名に鵠沼の名が付く地域がおよそ相当します。鵠沼神明や本鵠沼には路傍に石仏が多く残されていてそれらは元の位置から大きく動いてはいない印象がありますが、それでも最近移転となった塔がいくつかみられます。数年前まであった小さな神社が最近なくなった例もあります。これらの事情を尋ねてみると、地主や氏子の高齢化で維持が難しくなったという話をよく聞きます。これはこの地域に限られた話ではなさそうです。
| 鵠沼神明2-4-24 | 個人邸沿 | |||
| - | D像?丸 | 年不詳 | 風化著しく像容不明確 [K] は馬頭観音とするが持物より聖観音か | 石, K |
| 鵠沼神明2-14-18 | 辻 | |||
| 9-1 | A字個自 | 大正八 (1919) | 資, 総5, 石, K | |
| 鵠沼神明3-7 南東 | 共同墓地 | |||
| 9-2 | A字個柱 | 昭和十四 (1939) | ||
| 本鵠沼2-4-32 | 辻 | この二基は現在所在不明 [注1] | ||
| 9-3 | A字個駒 | 大正十 (1921) | 資, 総5, 石, K | |
| ー | X字?? | 大正十 (1921) | [K] によれば失われた | K |
| 9-4 | B像集駒 | 文化十三 (1816) | 二臂立像 六名の銘あり | 史, 総5, 石, K |
| 本鵠沼2-8-16 | 仲東の辻 | ここにあった塔は諏訪神社に移転 [注2] | ||
| ー | X字?? | 明治十九 (1886) | [K] によれば不明 | K |
| 本鵠沼2-15-1 | 辻 | |||
| ー | D像集丸 | 寛政九 (1797) | 風化著しく像容不明確な合掌像 [K] は馬頭観音とするが宝冠より聖観音か | 総5, 石, K |
| 本鵠沼3-3-32 | 路傍 | |||
| 9-5 | A像無舟 | 天保七 (1836) | 二臂立像 | 史, 総5, 石, K |
| 本鵠沼3-16 南端 | 本鵠沼三号踏切 | |||
| 9-6 | A字無尖 | 寛政十一 (1799) | 総5, 石, K | |
| 本鵠沼5-10 南側 | 苅田稲荷 | 同所に弘法大師像あり | ||
| 9-7 | A字個尖 | 昭和五(1930) | 総5, 石, K | |
| 鵠沼海岸7-5-18 | 堀川の辻 | |||
| ー | X字個自 | 明治二十八 (1895) | 現地になし | 資, 総5, 石, K |
| 9-8 | A字個自 | 大正十四 (1925) | 総5, 石, K | |
| 鵠沼海岸7-15-13 | 個人邸沿 | |||
| 9-9 | A字個尖 | 昭和二 (1927) | 同年の日付二つあり 二頭の馬の供養塔か | K |
| 鵠沼石上1-11 | 砥上公園 | 同所に庚申塔ほか多数の石碑あり | ||
| 9-10 | A字集駒 | 万延元 (1860) | 二名の銘あり | 史, 総, 石, K |
| 鵠沼石上3-1-25 | 個人邸内 | |||
| 9-11 | A字無柱 | 明治十五 (1882) | 風化が進んでおり銘読み取りにくい | 石, K |
| 鵠沼石上 | ||||
| ー | X字個尖 | 明治二十八 (1895) | [総5] には所在不明とある | 資, 総5 |
[注1] 2024年ごろまで現地にあったが再開発に伴い移転されたと思われれる 移転先不明
[注2] ここにあった馬頭観音塔と庚申塔は2021~2012年に片瀬の諏訪神社(下社)に移転した

手前 (1921) 後方 (1816)

祠内 (1836)
左の写真は本鵠沼の藤沢警察署から東250mほどのところにある二基の馬頭観音塔で、手前が文字塔、後方が像塔です。像塔には六名の銘が見られますが、右面の三名は鵠沼村の住人、左面のはたこ屋五良兵ヱ(北村五郎兵衛)と亀屋三左衛門は江の島の旅籠経営者、江戸新場中嶌忠治郎は江の島の青銅鳥居に中島屋忠治郎と見える人物と思われます。新場は新肴場河岸あるいは新場河岸と呼ばれた魚市場でした。この馬頭観音塔が建てれらた経緯はわかりませんが、この場所はかつて鵠沼から江の島に向かう街道沿いだったので、人馬の無事と商売繁盛を祈願したものだったのかもしれません。なお壬月とは閏月(文化十三年は閏八月)のことでしょう。
9-3 本鵠沼2-4-32 辻 駒形 大正十年 (1921)
[正面]大正十年 馬頭観世音 二月四日
[左面]施主宮崎正三郎
9-4 本鵠沼2-4-32 辻 駒形 文化十三 (1816)
[正面]〔二臂馬頭観音立像〕
[左面]施主淺場文次郎 同文七 板橋徳兵ヱ
[右面]江之嶋 はたこ屋五良兵ヱ|亀屋三左ヱ門 文化十三子壬月四日 江戸新場中嶌忠治郎
右の写真は、小田急本鵠沼駅から西350mのところにある小さなお堂の中に置かれている二臂像塔です。馬頭観音塔一基のためにお堂が建てられているのは市内ではここだけで、大切にされていることがうかがえます。塔には天保七年 (1836) の銘がありますが、施主の名前は刻まれていないようです。しかしこの像の前にある香炉に林氏とあり、林さんのご先祖が面倒を見ていた馬の供養塔でしょう。
9-5 本鵠沼3-3-32 路傍 舟型 天保七 (1836)
[正面]奉造立 〔二臂馬頭観音立像〕 天保七申七月吉日
【10.片瀬地域(片瀬村、江島)】
片瀬地域は、現在の地名に片瀬の名が付く地域ならびに江の島が相当します。藤沢宿から江の島に向かう旧江之島道沿いには庚申塔や道標を中心にさまざまな石碑が残されています。泉蔵寺には3か所に石碑群がありそれぞれ馬頭観音塔が複数基残っています。また江の島に残る2つの六観音はいずれも状態がよく、貴重な文化財と言えます。
| 片瀬2-18-3 | 泉蔵寺 | |||
| 10-1 | A像個舟 | 年なし | 参道にあり 二臂立像 | 総6, 石 |
| 10-2 | A字集尖 | 弘化五 (1848) | 参道にあり 台石を含め三十名の銘あり | 史, 総6, 石 |
| 10-3 | A字個弧 | 慶応三 (1867) | 境内にあり | |
| 10-4 | B字個自 | 明治四十三 (1910) | 境内にあり 「梵字ア」 三猿線刻あり | 総6 |
| 10-5 | A字個駒 | 天保十四 (1843) | 無縁墓域 | 総6 |
| 10-6 | A字個自 | 大正四 (1915) | 無縁墓域 | 総6 |
| 10-7 | A字個駒 | 昭和二十四 (1949) | 無縁墓域 | 総6 |
| 10-8 | A字個自 | 明治四十二 (1909) | 無縁墓域 「栗毛」 | 総6 |
| 片瀬2-19 西側 | 路傍 | 同所に庚申塔あり | ||
| 10-9 | A像個駒 | 天保五 (1834) | 三面八臂立像 | 史, 総6, 石 |
| 片瀬3-1 北端 | 諏訪神社 下宮 | 同所に庚申塔・道祖神・石祠あり | ||
| 10-10 | A字個柱 | 明治二十九 (1896) | 本鵠沼中東の辻より庚申塔とともに移設 (2021~2022年頃) | 資, 総5, 石, K |
| 片瀬3-13-37 | 龍口寺 | |||
| 10-11 | A字個自 | 昭和二十五 (1950) | 個人墓域 | 総6 |
| 10-12 | A字無自 | 年なし | 個人墓域 | 総6 |
| 10-13 | S像個舟 | 昭和六十 (1985) | 個人墓域 三面八臂立像 故人の供養塔 | 総6, 石 |
| 片瀬4-13-7 | 個人邸内 | |||
| ー | X字無自 | 年なし | 現地になし | 総6 |
| 江の島1-5-4 | 延命寺 | |||
| 10-14 | S像集舟 | 年なし | 六臂立像 六観音の一基 法名数名あり | 石 |
| 江の島2-5 | 第一岩屋 | |||
| 10-15 | S像個舟 | 寛文四 (1664) | 三面八臂座像 六観音の一基 | 石 |






上段の写真はすべて片瀬の真言宗寺院泉蔵寺にあるものです。左は参道に並べられた十基の石塔のうちのひとつで、二臂像と願主名が刻まれていますが年号がありません。馬の供養塔として造立されたものと思われますが、単独の馬頭観音像塔で年号がないのはあまりないと思います。中央は同じ場所にある文字塔ですが、左面に世話人二名、台石三面に二十八名もの名が刻まれており、村の馬持ちが勢揃いのようです。世話人の兵右衛門は片瀬の旧家浜野氏でしょう。
10-1 片瀬2-8-3 泉蔵寺 (参道) 舟型 造立年不詳
[正面]〔二臂馬頭観音立像〕 願主鈴木金右ヱ門
10-2 片瀬2-8-3 泉蔵寺 (参道) 角柱尖頭 弘化五 (1849)
[正面]馬頭觀世音
[右面]弘化五戊申年三月十八日
[左面]世話人 兵右衞門|勘治郎
[基礎正面]伊左衞門 豊治郎 重右衞門 万藏 源七 吉左衞門 長右衞門 源右衞門 甚右衞門 又左衞門 半左衞門 小右衞門
[基礎右面]孫治郎 金藏 惣左衞門 半右衞門 源兵衛 清藏 幸治郎 三良左衞門 㐂兵衞 松五郎 孫兵衞
[基礎左面]庄治郎 良助 作兵衞 友治郎 吉五郎
《原文》㔫(左)𱧊(源)垚(㐂)⿰氵⿱龶日(清)⿱助一(助)草書体(作)犮(友)
上段右の写真は同じ泉蔵寺の境内に整然と並べられた多数の石碑の中の一基です。写真では見えにくいですが、「馬頭観世音」と書かれた下に三猿の線刻があります。馬頭観音塔に三猿が描かれることはほとんどないと思います。これは庚申信仰にもとづく塔ではなく、個人の馬の供養塔に見えますがどうでしょうか。
10-4 片瀬2-8-3 泉蔵寺 (境内) 自然 明治四十三 (1910)
[正面]明治四十三天 〔梵字ア〕馬頭観世音 五月十八日
[正面下部]〔三猿線刻〕
[背面]施主 田中揔吉
下段左の写真は泉蔵寺の少し南の旧江之島道沿いにある小さな馬頭観音塔です。隣に立派な庚申塔があるので見逃してしまいそうですが、よくみると三面八臂座像が見られます。願主の傳右衛門は片瀬の人物と思われますが、同時代の片瀬の馬持ちの名がたくさん見える (10-2) の塔にはその名が見えません。下部は土に埋もれており台石はないように見えますが、あるいは台石も埋もれているのかもしれません。
10-9 片瀬2-19 西側 路傍 駒形 天保三 (1835)
[正面]〔三面八臂馬頭観音座像〕
[右面]天保五午十月吉日
[左面]願主傳右ヱ門
下段中央の写真は江の島の延命寺にある六観音の一体で、こちらで紹介したものです。延命寺はかつては小さな念仏堂で明治初年の神仏分離で廃寺となりましたが、今も大型の石碑がたくさん残されています。どれも状態がよいことに驚かされます。この馬頭観音の像容は典型的な憤怒像ですが、彫りは全体的に素朴に見えます。この六観音には造立年が刻まれておらずいつのものかわかりませんが、蓮華座に俗名や法名が記されており、念仏講による造立と思われます。
10-14 江の島1-5-4 延命寺 舟型 造立年不明
[正面]〔六臂馬頭観音立像〕
[蓮華座]十郎兵衛 道□ 教清妙吟 淨入智春 …… ……
下段右の写真は江の島の第一岩屋内にある六観音の一体で、これもこちらで紹介したものです。現在は六体は別々の場所に置かれていますが、造形や銘文から六観音として造立されたものであることは確実です。十一面観音の銘から江戸浅草の奥田九兵衛が寛文四年に奉納したことがわかります。造立目的は不明ですが、二世安楽でしょうか。これは藤沢市でもっとも古い馬頭観音塔と考えられます。六観音全体に像がきれいに残っており、洞窟の中で風雨にさらされることもなく今後も当分この状態を保てるでしょう。
10-15 江の島2-5 第一岩屋 舟型 寛文四 (1664)
[正面]〔三面八臂馬頭観音座像〕
[十一面観音の正面]武州豊嶋郡江戸浅草奥田九兵衛 寛文四年甲辰三月吉祥日 祇言