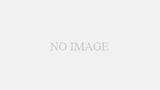今回から四回にわたって藤沢市内の馬頭観音塔をとりあげたいと思います。馬頭観音塔は数が多い割には庚申塔や道祖神塔ほど取り上げられる機会がありません。実際馬頭観音塔は、江戸時代後期以降に馬の墓標あるいは供養塔として造立されたものが圧倒的に多く、また様式的にも年号と施主の名だけを刻んだ文字塔が大半です。一方でこのようなステレオタイプとは異なる様式をもつ馬頭観音塔も少数ながら存在し、その中にはかなり興味深いものもあるのですが、それらについてあまり触れられることがないように思います。
そこでここでは現時点で市内で存在を確認している約150基の馬頭観音塔を簡略化したリストの形で示します。『藤沢の地名』(1990 日本地名研究所編)の区分にしたがい、市内を昔の村落にもとづいた10の地域に分けて地域ごとにまとめました。このうち像塔や特徴的な銘文を持つ塔などを中心に個別に銘文を紹介するとともに解説を付け加えています。あわせて、既存文献には見られるものの存在が確認できない塔もとりあげています。
表の二行目の記号の意味は以下の通りです。個々の馬頭観音塔の造立目的は必ずしも明確ではありませんが、様式や銘などから判断しています。
S:観音信仰にもとづく馬頭観音塔(多くは六観音供養や三界万霊供養などの目的をもつ)
A:馬の供養や安全祈念のための馬頭観音塔(馬頭観音の文字または像、年号、施主名を刻んだ典型的なもの)
B:馬の供養や安全祈念のための馬頭観音塔(典型的とは言えない様式あるいは銘文が含まれているもの)
C:現況は像容不明だが、既存文献などから馬頭観音塔と判断できるもの
D:既存文献に馬頭観音塔とあるが、馬頭観音塔とは認められないもの
X:既存文献に馬頭観音塔とあるが、存在が確認できないもの
字:文字塔 像:像塔
個:1名の記載があるもの 集:講や複数名の記載があるもの
無:名の記載がないもの
板:平板 柱:角柱 舟:舟型 弧:弧頭 尖:尖頭 重:重頭
自:自然 碑:板碑型 駒:駒型 丸:丸彫
表の五行目は既存文献を示します
史:藤沢市史第1巻(1970 藤沢市)
資:藤沢市史資料第18集(1974 藤沢市教育委員会)
総:藤沢市文化財総合調査報告書第1集-第9集(1986-1994 藤沢市教育委員会)
石:藤沢市の石仏(2003 藤沢市教育委員会)
U:打戻郷土誌(1998 打戻郷土誌研究会)
E:遠藤の昔の生活(1987 藤沢市教育文化研究所)
O:旧大庭村石造物(路傍)調査書(1995 大庭歴史研究会)
M:明治地区石造物調査報告書(2019 明治地区郷土づくり推進会議)
T:辻堂歴史物語 改訂版(2014 櫻井豊)
K:鵠沼地区の路傍石造物とモニュメント(鵠沼を語る会ホームページ内)
【1.御所見地域(獺郷村・宮原村・打戻村・用田村・葛原村・菖蒲沢村)】
御所見地域はほぼ現在の獺郷・宮原・打戻・用田・葛原・菖蒲沢に相当します。他の地域と比べて数多くの馬頭観音塔が見られます。この地域は昔の姿をより多く残しているため、開発にともなって失われたものが少ないからかもしれません。記録によれば宝永元年(1704)という古い塔があったようですが現地には見当たりません。
| 獺郷645 | 個人邸内 | |||
| 1-1 | A字個弧 | 大正七 (1918) | 明治九年の年号もあり二頭の供養塔か | |
| 1-2 | A字個弧 | 大正九 (1920) | 大正七年の年号もあり二頭の供養塔か | |
| 獺郷1200 | 辻 | 同所に道祖神あり | ||
| 1-3 | A像個舟 | 年不詳 | 二臂像 破損のため造立年不詳 | 総1, 石 |
| 獺郷1589 | 東陽院 墓地 | 同所に地蔵塔・廻国塔あり | ||
| 1-4 | A字個弧 | 明治六 (1873) | 総1, 石 | |
| 1-5 | A字無弧 | 文政十三 (1830) | 総1, 石 | |
| 1-6 | A字個弧 | 安政五 (1858) | 風化著しく年は[総1]引用 | 総1, 石 |
| 宮原3643 | 個人邸内 | 同所に庚申塔二基あり | ||
| 1-7 | A字無尖 | 嘉永五 (1852) | 総1, 石 | |
| 宮原 | 個人邸内 | |||
| ー | X字無尖 | 安政三 (1856) | これは嘉永五年塔の誤りか(注1) | 史 |
| 打戻658 | 個人墓地 | |||
| 1-8 | A字個駒 | 大正八 (1919) | 石, U | |
| 打戻1199 | 個人邸傍 | |||
| 1-9 | A字個自 | 昭和二 (1927) | 石 | |
| 打戻1286 | 個人墓地 | |||
| 1-10 | B字個碑 | 万治二 (1659) | 板碑型墓碑を再利用したものか | 石 |
| 打戻1321 | 個人墓地 | |||
| 1-11 | B字個弧 | 昭和三十二 (1957) | 北條時代の馬の供養塔? | |
| 打戻2587 | 妙福寺 墓地 | |||
| 1-12 | A字無板 | 年なし (現代) | 個人墓域にあり | |
| 1-13 | A字個尖 | 昭和四十五 (1970) | 無縁墓域にあり「馬名太郎」 | |
| 打戻2766 | 畦道傍 | |||
| 1-14 | A字個尖 | 大正十四 (1925) | ||
| 打戻2767 | ||||
| ー | X??柱 | 宝永元 (1704) | 現地になし あるいは(1-14)の誤りか | U |
| 打戻2789 | 畦道傍 | |||
| 1-15 | A字個尖 | 年なし | 石 | |
| 1-16 | A字個板 | 昭和四十九 (1974) | 石 | |
| 打戻3018 | 路傍 | |||
| 1-17 | A字個自 | 大正十三 (1924) | 宇都母知神社鐘楼のすぐ近くにある | U |
| 用田7-5 | 地蔵坂の辻 | 同所に道祖神塔・庚申塔・地蔵塔他あり | ||
| 1-18 | A字個弧 | 昭和十一 (1936) | 「昭和十年五月二十日亡」 | 資, 総1, 石 |
| 用田458 | 谷戸の辻 | 同所に道祖神塔・庚申塔・地蔵塔他あり | ||
| 1-19 | C字個自 | 明治十四 (1881) | 堂外で完全に風化 年は[総1]を引用 | 資, 総1, 石 |
| 用田705 | 寒川神社前の辻 | |||
| 1-20 | A字集重 | 明治三十三 (1900) | 「妙法」「施主連合仲間中」台石に馬の線画 | 資 |
| 用田1506 | 共同墓地 | |||
| 1-21 | A字個弧 | 昭和十二 (1937) | 個人墓域にあり | |
| 用田2734 | 個人墓地 | |||
| 1-22 | A字個弧 | 昭和二十八 (1953) | 石 | |
| 葛原318 | 辻 | 同所に題目塔と畜牛観音塔あり | ||
| 1-23 | A字個自 | 明治二十一 (1888) | 「南無妙法蓮華経」 | 石 |
| 1-24 | A字個自 | 明治三十三 (1900) | 倒れている「妙法」 | 石 |
| 葛原497 | 個人墓地 | |||
| 1-25 | A字個弧 | 昭和三十 (1955) | 「キングホープ」 | |
| 葛原862-8 | 路地奥 | |||
| 1-26 | A字個弧 | 明治七 (1874) | ||
| 1-27 | A像集弧 | 寛政十一 (1799) | 二臂像「相州高座郡葛原 中村 家村」 | |
| 葛原1919 | 瀧不動堂 | |||
| 1-28 | A字個弧 | 大正四 (1915) | 総1, 石 | |
| 1-29 | A字個自 | 大正五 (1916) | 総1, 石 | |
| 1-30 | A字個弧 | 大正八 (1919) | 「妙法」 | 総1, 石 |
| 1-31 | A字個弧 | 大正二 (1913) | 総1, 石 | |
| 葛原2477 | 路傍 | |||
| 1-32 | A字個自 | 明治三十二 (1899) | ||
| 葛原2553 | 辻 | 同所に庚申塔あり | ||
| 1-33 | A字個駒 | 昭和十五 (1940) | 総1, 石 | |
| 菖蒲沢890 | 浄土院 | 同所に庚申塔三基・巡礼塔・地蔵塔他あり | ||
| 1-34 | A字個弧 | 大正九 (1920) | 石 | |
| 1-35 | A字個弧 | 昭和八 (1933) | ||
| 1-36 | A字無弧 | 年なし (現代) | 石 | |
| 1-37 | A字無弧 | 天保十五 (1844) | 史, 総1, 石 | |
| 1-38 | A字個尖 | 嘉永四 (1851) | 史, 総1, 石 | |
| 菖蒲沢977 | 六地蔵の辻 | 同所に道祖神塔・地蔵塔あり | ||
| 1-39 | A字個柱 | 昭和三十一 (1956) | 「再建」 | 総1, 石 |
(注1) この塔は『藤沢市史資料22』(1978) によれば宮原1161の馬捨場跡にあったとされ、『藤沢市史研究42』(2009) によれば宮原1231の観音堂跡にあったもので個人邸に移設とある。また宮原3643の個人邸には同じ安政三年十一月の銘をもつ庚申塔があり、嘉永五年とあるべきところ誤って安政三年としたか





上段左の写真は中原街道(県道45号線)から150mほど東に入った獺郷中村集落の辻にある馬頭観音塔です。この隣には元禄元年の道祖神塔(今は存在しない)の大正七年の再建塔が立っています。元の道祖神は古くからこの集落の入り口を守っていたようです。馬頭観音塔の方は二臂合掌像が彫られており、正面に以下の銘文が刻まれています。残念ながら年号の部分が欠落していて造立年はわかりません。
1-3 獺郷1200 辻 舟型 造立年不詳
[正面]……戌二月日 〔二臂馬頭観音立像〕 常盤新蔵
上段中央の写真は打戻榎戸の個人墓地にある非常に古い年号をもつ馬頭観音塔で、以前こちらで紹介したものです。これが本当に万治二年に造立されたものであれば、例えば『馬と石造馬頭観音』(2000 神奈川新聞社)で紹介されている年号がわかる約四千基の馬頭観音のうち5番目に古い、貴重なものということになります。しかしこの碑の表面をみると文字は後刻に見えます。つまりこれは人間の板碑型墓碑をのちに馬頭観音塔として改刻流用したと考えられます。
1-10 打戻1286 個人墓地 板碑型 万治二(1659)
[正面]于時萬治二己巳 忠右ヱ門 馬頭觀世音 八月五日
上段右の写真は用田寒川神社の参道入口の辻にある明治三十三年の馬頭観音塔です。台石には線画で馬の姿が描かれている立派なものです。連合仲間中という言葉は聞きなれないですが、何名かの馬持ちのグループにより設立されたものでしょう。妙法とありますから日蓮宗系の仲間と考えられます。これは特定の馬の供養塔というよりは、馬や交通の安全を祈願するために建てられたものだと思われます。
1-20 用田705 辻 角柱重頭 明治三十三(1900)
[正面]妙法馬頭觀世音
[右面]明治三十三年三月九日
[左面]施主連合仲間中
[基礎正面]〔馬線画〕
下段左の写真にある辻は今は人通りも少なく寂しいところですが、かつては東は中村集落、北は宮下集落、南は皇大神宮、西は乗福寺につながる主要な辻だったようです。ここには二基の馬頭観音塔とともに「畜牛観世音」と書かれた大正四年の碑と、「南無妙法蓮華経 鬼子母神 十羅刹女」と書かれた明治二十五年の題目塔も置かれています。この題目塔の右面には、漆原忠左ヱ門氏が明治二十一年に日蓮宗に改宗した記念として造立したと記されています。(1-20)の馬頭観音塔の施主である連合仲間にも忠左ヱ門氏あるいは廣吉氏がいたのではないでしょうか。
1-23 葛原318 辻 自然 明治二十一(1888)
[正面]南無妙法蓮華経 馬頭觀世音菩薩
[背面]明治廿一年五月十七日 當所 漆原忠左ヱ門
1-24 葛原318 辻 自然 明治三十三(1900)
[正面]妙法 馬頭観世音 明治丗三年十月二日 漆原廣吉
下段右の写真は葛原芝地の民営墓園の北側の細い行き止まりの道の奥にある馬頭観音塔二基で、以前こちらで紹介したものです。(1-26)の施主は(1-23)の漆原忠左ヱ門その人です。明治七年ですから改宗前ということになるでしょう。このあたりはかつて葛原村、上土棚村、深谷村の三村の境界にあたるところでしたので、これらの塔は馬や交通の安全を祈願したものかもしれませんが、集落からは少し離れていて川に近いことから、かつて近くに馬捨場があったのかもしれません。
1-26 葛原862-8 路地奥 角柱弧頭 明治七(1874)
[正面]馬頭觀世音
[右面]明治七戌十一月吉日
[左面]葛原村 漆原忠左ヱ門
1-27 葛原862-8 路地奥 角柱弧頭 寛政十一(1799)
[正面]〔二臂馬頭観音立像〕
[右面]寛政十一戊未十一月吉日
[左面]相州高座郡葛原 中村|家村
【2.長後地域(長後村・七ツ木村・千束村・下土棚村)】
長後地域はほぼ現在の長後・高倉・下土棚・土棚に相当します。馬頭観音塔の数は多くありませんが、開発のため移動されたり失われたものがいくつもあるので、おそらく昔はもっとあったと思われます。ほとんどの共同墓地は地域の開発にともなって新たに造られたものなので、そこにある墓碑などの石碑は個人墓地から移動されたものです。
| 高倉983-1 | 地蔵の辻 | 同所に地蔵塔あり | ||
| 2-1 | A像無舟 | 寛政十 (1798) | 二臂座像 上部破損 | 総2, 石 |
| 高倉1155 | 辻 | |||
| 2-2 | B字集自 | 年なし | 「大德 松波天助」 | 石 |
| 高倉2273 | 個人邸傍 | |||
| 2-3 | C字個板 | 明治三 (1870) | 風化激しく倒壊 年号は[総2]引用 | 総2, 石 |
| 高倉886 | ||||
| ー | X字無尖 | 昭和三 (1928) | 現地になし [石]によれば「妙法」 | 石 |
| 高倉2375先 | ||||
| ー | X字個尖 | 昭和三 (1928) | 現地周辺になし あるいは(2-3)の誤りか | 資 |
| 下土棚999 | 善然寺 | |||
| 2-4 | A字集駒 | 万延二 (1861) | 「相州高座郡下土棚村」 | 史, 総2, 石 |
| 下土棚1108 | 共同墓地 | |||
| 2-5 | A字個板 | 昭和三十八 (1963) | 個人墓域にあり | |
| 下土棚1981? | ||||
| ー | X字個? | 昭和四十四 (1969) | 現地になし 開発で現地は変貌している | 石 |
| 土棚644 | 共同墓地 | |||
| 2-6 | A字個弧 | 昭和六 (1931) | 個人墓域にあり | |
| 2-7 | A字個柱 | 年なし (現代) | 個人墓域にあり「名馬くろがね」 | |
| 長後513 | 長後市民センター | 多数の石碑が集められている | ||
| 2-8 | A字個重 | 嘉永六 (1853) | 元位置不明 | 総2, 石 |
| 2-9 | A字個柱 | 大正四 (1915) | 元位置は仙元塚付近(下土棚509) | 総2, 石 |
| 長後1992 | 辻 | 同所に墓碑一基あり | ||
| 2-10 | A像集舟 | 年不詳 | 二臂像 上部損傷大きく造立年不詳 [石]によれば「念仏講」とあった | 石 |
| 2-11 | A像個舟 | 天保五 (1834) | 二臂像 | 石 |
| 長後2346 | 個人墓地 | |||
| 2-12 | A字個自 | 昭和十五 (1940) | ||
| 長後2656-1 | 辻 | |||
| 2-13 | B字個弧 | 明治二十七 (1894) | 「陸軍徴発馬匹」 | 総2 |



上段左の写真は県道22号線七ツ木市民の家入口交差点にある馬頭観音塔で、同所には恵母地蔵と呼ばれている、子供を抱えた行き倒れの女性を弔ったとの伝説のある明和五年(1768)の地蔵菩薩像が祀られています。この馬頭観音塔はかなりもろい火山岩に彫られているうえ、上部が欠けており文字が一部読めなくなっていますが、かろうじて寛政十年とあったことがわかります。一方で合掌する二臂座像はきれいに残っています。この塔は馬の供養塔と思われますが、読み取れる情報が少なく断定は困難です。
2-1 高倉983-1 辻 舟型 寛政十(1798)
[正面] ……十午天 〔二臂馬頭観音座像〕 ……月吉日
上段右の写真は長後西北部の上谷集落の辻にある馬頭観音塔です。陸軍徴発馬匹と書かれていますが、年号から見て日清戦争で徴発された馬の供養塔と思われます。馬の徴発の歴史については、相模原市のホームページ『第23回企画展 「兵事書類と馬~町村役場資料に残る馬匹書類から考える~」』(こちら)の記事が非常に参考になります。
2-13 長後2656-1 辻 角柱弧頭 明治二十七 (1894)
[正面] 明治廿七年十一月二日 陸軍徴発馬匹 馬頭觀世音 施主 石井豊次郎
《原文》㞷(徴)
下段の写真は長後駅入口交差点から北西に伸びる市道(長後865線)の綾瀬市との境界付近にある三基の石碑です。左は馬頭観音塔で、右は頭頂部が欠落していますがこちらも馬頭観音塔でしょう。どちらも二臂で合掌している立像が彫られています。中央は墓碑で正面には「水縁自清道者」と書かれており右面には明治三年(1890)の年号があります。『藤沢市の石仏』によれば左の塔には念仏講という文字があったようですが、造形的には馬の供養塔です。村はずれの辻に置かれたこれらの石碑には何か謂れがあると思われますが、ここをお世話している人はいないように見え、手掛かりはありません。
2-10 長後1992 辻 舟型 造立年不詳
[正面] ……辰十二月吉日 〔二臂馬頭観音立像〕 念仏講 長後村上谷
2-11 長後1992 辻 舟型 天保五(1834)
[正面]天保五甲午三月吉日 〔二臂馬頭観音立像〕 長後上谷村 井上勘右ヱ門