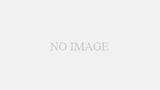藤沢北部の御所見地区はかつて菖蒲沢・葛原・用田・打戻・獺郷・宮原の6つの村からなっていました。現在その名は藤沢市の大字として地名に残っています。このうち打戻は御所見地区南部に位置しており、この地域は今のところ大規模な宅地開発を免れているため昔の姿を残した田園風景が南北に広がっています。打戻の中央東部にある宇都母知(うつもち)神社は千年以上の歴史があるとされ、打戻の名称は宇都母知から転訛したとも伝えられています。
打戻の中央には藤沢市道遠藤宮原線が東西に走っています。この道路は打戻の東に接する遠藤の慶応大学湘南藤沢キャンパスの建設と同時期に作られた新しい幹線道路です。この遠藤宮原線の榎戸交差点の西北に位置する旧家山崎家の墓地の近くに一基の馬頭観音塔が立っています。しばらく前までこの塔は草に埋もれていたのでその場所を知っていなければ見つけることは困難でしたが、最近草がきれいに刈り取られて銘文がよく読み取れるようになっていました。

1 打戻1286 個人墓地外 板碑型 万治二年 (1659)
[正面]于時萬治二己巳 忠右ヱ門 馬頭觀世音 八月五日
馬頭観音塔は近世以降馬の供養塔として造られることが多く、この馬頭観音塔もかつてこの旧家のご先祖が世話をしていた馬の墓碑なのでしょう。しかしこの塔は墓域から少し離れたところにあります。個人の所有地に建てられた屋敷墓などでは、馬の墓碑である馬頭観音塔はしばしば人間の墓域には入れてもらえず、その外側にぽつんと建っていることが多いのものです。しかし都市化のための区画整理などで屋敷墓が近代的な集合墓地に移転されると、自分の墓域以外には墓石を置けなくなって馬頭観音塔もめでたく人間の墓碑と一緒に並べられることになります。
藤沢市内の馬頭観音塔は140基~150基ほど確認していますが(馬頭観音塔かどうか微妙なものがいくつかある)、個人の邸宅内にあるなど現存していても知られていない塔は他にもまだたくさんあると考えられます。一方で過去の文献には記載されているものの、今では失われたと考えられるものも少なからずあります。これは、村や講という集団で造立された供養塔とは異なり、個人が世話していた馬の供養塔はその性格上代々供養されることが少ないからだと思われます。
ところでこの馬頭観音塔にはいつくかの特徴があります。まず形式が古い板碑型であることで、馬頭観音塔でこの形式は珍しく藤沢市内にはこれしかありません。そしてそこに刻まれた年号も馬頭観音塔としてはかなり古いものです。この塔は『藤沢市の石仏』(2003 藤沢市教育委員会)ではじめて紹介されたようで、そこには銘が明治二年と書かれていますが実物を見ると万治二年(1659)と刻まれており、藤沢市に残る最も古い年号を持つ馬頭観音塔ということになります。六観音や七観音のひとつとして造られたものを除けば、次に古いものは村岡東にある享保十年(1725)の塔ですからそれよりも60年以上前です。
このあたりでは馬頭観音塔は1800年前後から急に造られ始め、それ以前のものはわずかしかありません。しかも個人の墓地に飼い馬の供養塔として馬頭観音塔が造立されるのはほとんどが江戸時代後期以降であり、この塔のように当時の人間の墓碑とまったく同形式で造られるというのは江戸時代初期としてはきわめて例外的に思われます。ちなみに現在藤沢市内に残る江戸時代中期まで(~1780)の年号をもつ石塔で単独の馬頭観音塔と確認できるものはこれ以外に三基ありますが、いずれも屋敷墓に建立されたものではありません。それらを以下に紹介します。


2 村岡東2-167-8 路傍 舟型 享保十年 (1725)
[正面]〔八臂馬頭観音立像〕 造立願主 願誉浄念比岳
[背面]享保十乙巳年十一月日 高谷村弥陀堂八王山西福寺 三界万靈有無両縁
[背面下部]寄附施主 西歸比岳 清兵衛 渡内 六良兵衛 元右門
《原文》岳(ママ)陁(陀)㚑(靈)
3 柄沢1-7-1 隆昌院 角柱尖塔 明和八年 (1771)
[正面]馬頭觀世音菩薩
[右面]馬捨塚
[左面]明和八辛卯四月日 願主 金井四郎右衛門
2番は廃寺となった旧高谷村阿弥陀堂にあったとされる馬頭観音塔で、これは三界万霊塔として建てられたものであることが銘文からわかります。像容は八臂の憤怒相で本来の馬頭観音の姿に近いものです。時代が下ると以前紹介した葛原の馬頭観音塔(詳細はこちら)のように穏やかな顔になっていきます。3番は柄沢の隆昌院にある馬頭観音塔で、これはかつて各村にあった馬捨場と呼ばれる死馬を遺棄する場所にあったものであることが銘文からわかります。馬捨と明示されているのは藤沢市ではこの塔だけですが、それ以外にも今に残る馬頭観音塔のうちいくつかは馬捨場に建てられたものであったと思われます。

4 西富1-9-27 長生院 角柱尖塔 宝暦五年 (1755)
[正面]宝暦五乙亥歳 為馬□神祭祠 〔梵字馬頭観音〕馬頭觀世音菩薩 七月廿四日 藤澤道場
4番は小栗伝説で知られる西富の遊行寺長生院にあり、この伝説に出てくる鬼鹿毛という馬の供養塔とされているものです。表面の風化が激しく銘文は一部読み取れないので『藤沢市文化財総合調査報告書9』(1994 藤沢市教育委員会)を参考にした部分は赤字で示しています。銘文によればこの塔はかつて存在した祠にあったようですが、小栗伝説との関係はよくわかりません。また左右に見えるくぼみは、かつてこの石柱が何かの支柱として、あるいはより大きな構造物の一部として利用されていたことを示しています。いずれにしてもこの塔は小栗伝説の遺跡のひとつとして長生院の参詣者獲得に貢献していたことでしょう。
さて万治二年塔に話を戻します。ここからは私見になりますが、江戸時代初期としては例外的なこの塔は最初から馬頭観音塔だったのではなく、どこかの時点で人間の墓碑に馬頭観世音と改刻したのではないでしょうか。石碑の再利用や改刻はしばしば見られるものです。年号や日付も改刻されているかは何とも言えませんが、万治二年の干支は本来己亥のところ己巳と刻まれおりかなりずれています。ちなみに『藤沢市の石仏』にあった明治二年ならば己巳と整合します。改刻だとしたらこの頃だったのかもしれません。しかしこの馬頭観音塔が改刻であったにせよそうでなかったにせよ、忠右衛門氏は愛馬を人間と同じように大切にされていたことがこの素朴な彫りから感じられます。