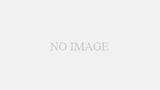藤沢市北東部の境川西岸沿いに南北に広がる高倉は、江戸時代には北部の千束村と南部の七ツ木村から成り立っていました。『新編相模国風土記稿』(1841)によれば、この二村は元々ひとつの村であったのが、元禄の頃に千束村が七ツ木村より分かれたとあります。明治十六年に両村はふたたび合併して高倉村となり、これがほぼ現在の高倉にあたりますが、区画整理(北部第一土地区)により昭和五十九年にその最南部は湘南台六丁目になりました。高倉の境川沿いは今も稲作が行われており、その雰囲気は西俣野に共通するものがあります。
現高倉の最南部、湘南台との境に14世紀に創建されたと伝えられる臨済宗寺院の東勝寺があり、その墓地西北角に子育地蔵と呼ばれる石造の地蔵菩薩がお堂に祀られています。このお堂はいつもきれいにされており、また地蔵の衣装も季節にあわせて着せ替えられるなど地元の人々に大切にされていることがわかります。下の写真は4月に撮ったものですが、3月に訪問した時にはこのお地蔵さまは下にセーターを着ておられました。


この地蔵菩薩塔の銘文は以下の通りで、延享三年(1746)に建立されたことがわかります。基礎石に観音講とありますが、像容は錫杖と宝珠をもつ典型的な地蔵菩薩立像です。風化のため人名はあまり読みとれませんが、かろうじて読みとれた文字からは今も続く高倉南部の旧家の苗字がうかがえます。また子育地蔵らしく母と刻まれた人名が多く、女性が講の中心であったことが見てとれます。なお赤字は『長後誌史』(1967)ならびに『藤沢市文化財総合調査報告書第2集』(1987)を参考に補いました。
地蔵菩薩塔 丸彫 延享三(1746)
[正面] 〔地蔵菩薩立像(錫杖・宝珠)〕
[基礎正面]延享三丙寅天 観音講供養 八月吉日
[基礎右面]施主 小山……母 綿……母 ………… 塚本…… 斉藤……
[基礎左面]城染 神山利右ヱ門母 同与兵衛母 同伊左ヱ門母 同五左ヱ門母 岸田勘左ヱ門
この中に城染という、僧侶と思われる名がみられます。染の文字は読み取りにくいのですが、同じ名が東勝寺の400mほど北に位置する七ツ木神社の石碑にも見られるので、間違いないでしょう。七ツ木神社は旧七ツ木村の鎮守だった村持ちの神社で、新編相模国風土記稿には鯖神明社と記されています。この神社には道祖神塔、庚申塔、養蚕信仰塔、御嶽信仰塔などさまざまな石碑が残されていますが、その拝殿左側の斜面には、ひっそりと三基の石碑が置かれています。

一番右は明治二十一年の御嶽信仰塔であり、裏面には以前亀井神社の項で紹介した(こちら)亀井野行者長谷川長清の名が見られます。また基礎石には七ツ木村をはじめ近隣の村々の25名の氏名が刻まれています。そして中央の半ば埋没している流造の石祠には次のように刻まれており、ここに城染の名前が見られます。
石廟 流造 延享二(1745)
[廟身右面]延享二乙丑天 九月吉日 施主 城染
[廟身左面]相州高座郡 七木郷
延享二年(1745)は子育地蔵建立の一年前ですから、2人の城染は同一人物とみてよいでしょう。そしてさらにもう一か所、旧七ツ木村で城染の名が見られるところがあります。それは大日如来祠です。七ツ木神社の東の道をさらに北に行くと、七ツ木の旧家のひとつ澤野氏によって造立されたと伝えられる大日如来祠があます。江戸時代末の記録によればこのあたりは大日の森と呼ばれており、森林だったようです。現在ここには二基の大日如来塔と三基の石祠、そして再建塔と思われる新しい道祖神塔などが祀られています。

この鳥居前には最近立てられた看板があり、この祠の由来やここにある主な石碑の銘文が示されており大変参考になりますが、若干の誤りや欠落も見られます。そこでここでは以下にこの大日如来祠にあるすべての石碑の銘を示します。風化あるいは剥落のため読み取れない部分は、藤沢市文化財総合調査報告書第2集(1987)と藤沢市の石仏(2003)を参考にして赤字で補っています。この場所に残されている全部で10基の石碑のうち上の写真の石段右側に1,2があり、下の写真の手前に3、中央左右に4,5、奥に6,7,8、奥右手に9が見えます。

1 道祖神塔 舟型 造立年不明
[正面]七木村 〔二神立像〕(著しく風化)
2 道祖神塔 舟型 平成十四(2002) (上記の再建塔)
[正面]〔二神立像〕
[背面]奉納 平成十四年一月吉日 渡貫直正
3 石段標石一対 角柱尖頭 明和七(1770)
[右正面]明和七寅年 十一月吉祥日
[左正面]施主當村 沢野徳右ヱ門
4 大日如来塔 舟型 明和七(1770)(左側)
[正面] 明和七寅年 施主 當村 〔大日如来立像(智拳印)〕 四月吉日 沢野徳右ヱ門
5 大日如来塔 丸彫 造立年不明(右側)
[正面] 〔大日如来立像(定印)〕(上部欠)
[基礎左面]志主 四月一日城染
6 石廟 流造 宝暦七(1757)(左側)
[廟身正面]中村 沢野徳右ヱ門(本来この面は右面)
[廟身左面]地神宮 □□七丁□八月吉日(本来この面は正面)
7 石廟 流造 平成二十七(2015)(中央 9の再建塔)
[廟身背面]平成二十七年三月吉日 氏子中
8 石廟 流造 寛保三(1743)(右側)
[廟身背面]寛保三亥天 奉納御寶前 沢野徳右ヱ門(本来この面は左面)
9 石廟 流造 延享五(1748)(倒壊して片付けられている)
[廟身右面]延享五戊辰年 六月吉日
[廟身左面]講中 四月朔 沢野
10 石廟 切妻平入(奥 銘なし)
1番の道祖神塔と思われるものは原型をとどめないほど風化しており何も読み取れません。5番の大日如来塔は上部が欠落しているため、尊名は確認できない状態です。また9番の石廟は残欠と思われるものが現地に残っていますが、土中に埋もれており銘は確認できません。10番は厳密にはこの大日如来祠の敷地内のものではないのかもしれませんが、3つの石廟のさらに奥にあります。ここに何度も登場する沢野徳右衛門は、ここから少し西の県道横浜伊勢崎線沿いの澤野家墓地に供養塔があり、それによれば寛政十一年(1799)に亡くなったとあります。
城染の銘のある5番の大日如来塔には年号がありませんが、ここにある他の石碑の年号(1743年から1770年まで)から見て、これも子育地蔵や七ツ木神社の城染と同一人物でしょう。ところで他文献では正しく読み取れていませんが、5番の基礎石左面はよく見ると「四月一日城染」と刻まれています。また記録によれば9番の左面には四月朔と書かれていたようですが、その右面には延享五戊辰年六月吉日という日付がすでに書かれています。とすると四月朔は何を示していたのでしょうか。四月朔や四月一日というのは日付ではなく、苗字だったのではないでしょうか。
『寒川町史調査報告書2』(1993)には、高野山高室院の檀廻帳に記載された人名の一覧が村ごとに分類して掲載されており、これによれば江戸時代七ツ木村には次の苗字をもつ人物がいたことがわかります。
岸田、神山、岩崎、斎藤、沢野、塚越、四月朔日
この檀廻帳は宝暦二年(1752)のものなので、城染の時期と完全に一致します。四月朔日や四月一日はわたぬきと読み、綿貫・渡貫に通じる苗字です。実際2番の道祖神塔の奉納者は現代の渡貫さんで、他の苗字もすべて今も高倉で見られるものです。とするとこの大日如来祠は沢野氏と四月朔日氏によるもののように思われます。またあらためてよくみると東勝寺の子育地蔵の写真右奥には綿貫という札が見えています。城染がどの寺院と関係があったのかはわかりませんが、渡貫さんのご先祖で、当時沢野徳右衛門とともに村の有力者であったと言えそうです。
私の知る限り藤沢市内で四月朔日や四月一日との苗字はこの大日如来祠以外には見られず、また高倉ならびにその周辺の石碑で綿貫や渡貫という苗字が見られるのは明治以降なので、四月朔日や四月一日との記述がいつまで使われていたのかは不明です。そもそも当時一般庶民が苗字を書きしるす機会はきわめて限定的であったことを考えると、高野山の記録がいかに貴重なものであるかがよくわかる例となりました。